| « 2006年10月3日 | 2006年10月6日の投稿 |
2006年10月11日 » |
yachさんのブログより。
http://d.hatena.ne.jp/yach/20060927
ソフトウェアの変更は、そのソフトウェアに関わる人間の活動によって発生する。人間の活動には周期があり、その周期によって発生する変更の内容も変わってくる。変更は種類に応じて周波数を持つことになるので、その周波数をソフトウェアの設計で考慮することで、「変更を予測」せずとも、変更に強い設計が得られる。
そういえば、この「変更周波数」というアイディアは、ぼくも考えたことがあった。
http://blogs.itmedia.co.jp/hiranabe/2005/08/_eocease_of_cha_602c.html
yachさんは、この周波数が「人間活動」に関連していることに気づいている。
また、これらをふまえた、ぁまんにょさんの「リズムについて」
http://d.hatena.ne.jp/amapyon/20061005
も面白い。TOCのドラム・バッファ・ロープに繋げている。
ぼくは、PFの中で、リズムを「行動の搬送波」と捉えているが、それを「ソフトウェアの変更」とは未だに結び付けて考えられていなかった。もしかしたら、何かミッシングリンクが繋がる予感が…。
我が師、Ron Jeffries のブログより。
http://xprogramming.com/xpmag/RubyFitnesse.htm
Fitnesse(フィットネス)は、ユーザテスト(受け入れテスト)のツール。ユーザは「表形式」を好む、ということで Wiki でもってテストを表駆動でやろう、という発想(これも、Ward Cunningham が最初に FIT というツールを書いたのが始まり)。
このブログでは、これを Ruby からやってしまおう、ということらしい。詳しくはまだ読めていないが、どなたか解説をトラバなどしてくれないだろうか。。。。。
チェンジビジョンのTRICHORDチームは、今までぼくが見たプロジェクトの中では、最もストリクトにアジャイル開発を実践しているチームの1つだ。彼らが取り入れているプラクティス(実践項目)の中には、「ペアプログラミング」や「コード共有」などのXPに起源を持つ物も多いが、問題解決あるいはアイディアとして自分たちで試し、うまくいったものに名前を付けて定着させる、というループが回った結果として出てきたものもある。こうしたうまくいったことの集大成として、現在行っているプラクティスセットがある。このプラクティスセットを、今回発表した。
http://trichord.change-vision.com/blog/2006/10/929_1.html
例えば、オリジナルプラクティスとして、
バグレゴ: バグを物理的にレゴブロックを積んで表現する
ワークスペースメイキング: 自分たちの手による部屋の模様替え
リリースゴール共有: ストーリだけでなく、全体感イメージをマインドマップで共有
リリースタイムアタック: リリース作業の時間を計測し、タイムを上げていく

 などなど、とっても豊富。この資料は、彼らの「経験と知恵のスナップショット」をまとめたものである。アジャイル開発にトライしているチームは参考にしてもらえるとうれしい。また、上記URLのブログにフィードバックなどいただけると、もっと嬉しい。
などなど、とっても豊富。この資料は、彼らの「経験と知恵のスナップショット」をまとめたものである。アジャイル開発にトライしているチームは参考にしてもらえるとうれしい。また、上記URLのブログにフィードバックなどいただけると、もっと嬉しい。
| « 2006年10月3日 | 2006年10月6日の投稿 |
2006年10月11日 » |
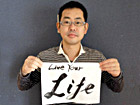
 顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立
顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う
ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方
悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か
考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック
なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント
部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命
第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命