| « 2010年10月10日 | 2010年10月11日の投稿 |
2010年10月12日 » |
クラウドコンピューティングが広がりを見せていくと、ユーザ側は情報の保存場所をあまり意識をする必要はなくなりますが、クラウドサービスを提供する事業者や政府は、これまで以上に提供する場所を意識するようになってきています。
ジャーナリストの小池良次氏が、10月9日の「日本は次世代ITサービスで生き残れるのか クラウド保護主義と国際データ・センター誘致競争」記事の中にはいくつか興味深い内容が書かれています。
一部の欧州諸国では、ユーザーのデータの海外保管を禁止する措置にでており、米連邦政府もガーバメント・クラウドでは、データの海外流出を認めていない。このようにクラウドは国境を越えてサービスを利用することが当たり前となっていながら、既存のルールや規制により越境を認めない矛盾した状況にある。
米国のハイテク業界では、こうしたクラウド保護主義の台頭に警戒感を強めており、クラウド・オープン化外交の積極的な展開を米国政府に求めている。
中国は国内で独自のクラウド・システムとクラウド・ビジネスを展開するようになるだろう。また、中国に追従し、中東諸国がクラウド保護主義に走ることも懸念される。これは米国のクラウド産業にとって大きな損失となるだけでなく、日本にとっても大きな痛手となるだろう。
米国や欧州、そして中国等、自国からの情報流出を避けるため、様々な政策をとってきています。米グーグルは「Google Apps for Government 」や米マイクロソフトは「Microsoft in Federal Government」などは、政府向け独自のクラウドサービスを展開しており、政府向けの強化をしています。一方でクラウド事業者としては、世界市場をターゲットとするのであれば、政府が進めている保護主義に対して警戒感を強めていくことでしょう。
小池氏の記事の中では、米国防省が、世界のクラウド市場を確保できるように、国際協調体制の構築に乗り出し、第一歩として日米協議の合意書をあげており、日本が重要なパートナーに選ばれた理由として以下のとおり、書かれています。
海底ケーブルなど国際通信網的にみて日本は中国に近い。しかも北アジアで最大級の情報通信市場を抱えている。また、日本はインターネット黎明期から、MIME規格(電子メールのタイトルにアジア言語を使えるようにする規格)やIPv6の開発整備などで重要な役割を担ってきた。
現在も、上位DNS(ドメイン・ネーム・サーバー)の運営管理をおこない、ネット・コミュニティーにおいて、大きな影響力を持っている。しかも、米国と日本はネット規制環境的にも似た立場にある。こうした観点から考えると、日本は対中国対策でもっとも適切な相手といえるだろう。
一方、日本にとっても、米国との協調体制を確立することは重要だ。既に述べたように、日本の企業や個人は米国のクラウド・サービスを頻繁に利用している。ネット・セキュリティーや通信の秘守、プライバシー保護、著作権保護などにおいて、日米に共通するクラウド市場を形成することは日本企業にとって大きなメリットとなるだろう
現在、日本には、クラウドサービスの提供に関する安全保障についての法制度が確立されておらず、日米でのクラウド市場において合意形成を政策的につけておくことは、非常に重要となってくるでしょう。
日本では、「データセンターの特区創設と国内立地推進について(まとめ)」でもご紹介したように、石狩や松江などにおいて、郊外型のデータセンター設置の動きがあり、政策的には、特区の創設や自治体の誘致も始まっています。最近では、ヤフーとIDCフロンティアが10月8日、福島県白河市に「新白河データセンター(仮称)」を建設すると発表し、2012年3月末の竣工を計画しています(関連記事)。
「新白河データセンター(仮称)」の完成予想図
クラウドコンピューティングの普及が進めば、必然的にそのインフラとなるデータセンターは増えていきます。アジア等の新興国のユーザが、クラウドを積極的に利用するようになれば、どこの国からクラウドサービスを提供するというのは、ビジネスにとっても政策にとっても重要となるでしょう。データセンターの設置は、国内市場だけを意識したものになれば、市場は縮小の方向に向かうのではないかと考えられます。
クラウドコンピューティングが進めばサービスレイヤでの覇権争いやビジネスモデルの展開はもちろん重要で大前提としてあります。ただし、日本はサービスレイヤーにおいては苦戦を強いられているのが現状です。現在、シンガポールがデータセンターを政策的に積極的に誘致し、アジアの情報のハブとしての地位を確立しつつあります。日本も情報の集積地となるような、国際競争を意識した展開が今後益々重要となっていくのではないかと感じています。
| « 2010年10月10日 | 2010年10月11日の投稿 |
2010年10月12日 » |
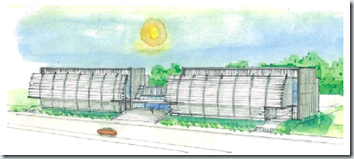

 顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立
顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う
ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方
悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か
考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック
なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント
部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命
第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命