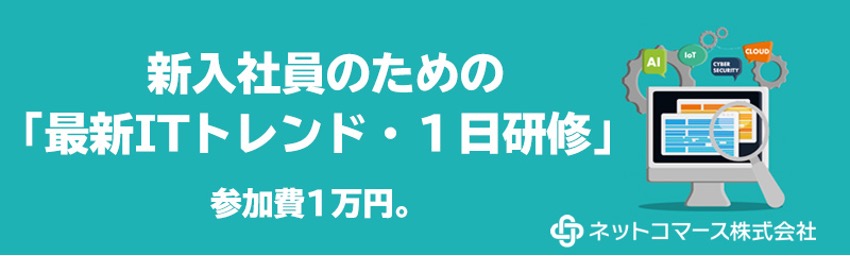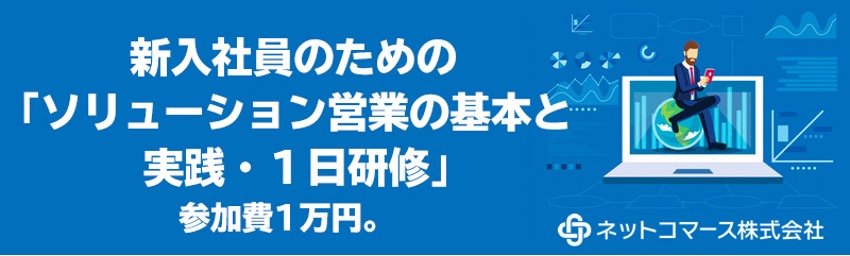溶けるプログラマー・沸き立つエンジニア
「IT人材不足」の根幹にある「学ばない日本人」問題
なぜ、日本人は学ばないのかについては、先日のブログで紹介した「学ばない日本人」問題があります。
「世界の中でも圧倒的に学ばない日本人に学ばないことへの積極的な理由や学ばないことの明確な原因など存在しないということです。こうした日本人の学びそのものの消極性と意志のなさこそが、この問題の核心です。−中略−日本人は学ぶ意欲があるのに何かの障害があるわけでもなく、学ばないぞと主体的に選んでいるわけでもなく、なんとなく学んでいない。息をするように当たり前に学ばない日本人に対して、いくら時代が変わるからリスキリングが必要だからとお説教しても、効果が薄くて当然でしょう。(リスキリングは経営課題・小林祐児 著・光文社新書)」
「なんとなく学ばない」背景には、学ばなくても何とかなっている現実があるとも指摘しています。
高度経済成長時代の惰性とでも言うべきでしょうか、自らの意志で学ばずとも、急成長する社会の需要に応えていれば、企業は成長できました。また、変化に対処するよりも、生産性の向上やコストの削減に重きが置かれていた時代でもあり、従業員は、所与の仕事をこなし、その延長線上でスキルを磨けば、企業の成長に貢献できたわけです。もちろん、いまは高度経済成長の時代ではありませんから、これが許される環境にはありませんが、企業に深く根付いた風土や文化は、そう簡単に変わらないのも現実です。
IT業界も同様です。高度経済成長の拡大する需要に応えようと、1970年代からの構造化プログラミングやウォーターフォール開発が、積極的に取り入れられました。50年以上前の話です。もはやこの常識が、時代にそぐわなくなったいまでも、当時の莫大な遺産に支えられ、未だに過去のやり方をそのままに変えようとしていません。例えば、開発・実行環境がクラウドになっても、何の疑問も持たないままに、過去のやり方で仕事を続けるIT企業が少なくないのは、こんな現実があるからです。
アジャイル開発やDevOps、サーバーレスやコンテナ、マイクロサービス・アーキテクチャで開発し、GitHubでコードを管理するなどのいまの常識を、「特別」「新しい」「進んでいる」という言葉で表現する人がまだまだ多いのを見ると、「学ばない」という現実が、いかに身近であるかが分かります。
プログラマーが溶けてなくなる
そんな惰性が通用しない時代になりました。例えば、BolltやDevine、ReplitといったAI駆動開発の登場により、システム開発に関わる知的力仕事(パターン化された知識労働)は広範に置き換えられつつあります。
これは、工数需要を収益基盤とするSI事業者やSES事業者にとっては、死活的な脅威です。プログラマーと称する「コーダー」という職業が、溶けてなくなってしまうわけで、事業基盤を維持できなくなります。一方で、「IT人材不足」が、「プログラマー(コーダー)人材不足」であるとすれば、この問題は、一気に解消してしまうでしょう。
「システム開発」の再定義が迫られる
しかし、そう簡単な話ではありません。「IT人材不足」の本質は、「プログラミングに関わる要員(コーダー)」が足りないという問題ではなく、「システム開発のための要員(真の意味でのエンジニア)」が不足することを意味しています。そうなると、「IT人材不足」は、「スキルのミスマッチによる人材不足」が、問題の本質となります。
本来、「システム開発」とは、「ビジネス上の課題をあきらかにして、これを解決するための仕組みを作る一連のプロセス」です。プログラミングは、このプロセスの一部です。
- ビジネス上の課題を定義する。
- これを解決するための戦略を策定する。
- 戦略を実行するための手段を決定する。
プログラミング以前に、課題定義、戦略立案、ルールや規則、業務手順の作成など、システム開発でやるべきことは沢山あります。こういう作業も含めて、「システム開発」と捉えるのが本来の解釈です。ここにスキルが求められているのです。まさにこの点に於いて、「スキルのミスマッチによる人材不足」が、顕在化するでしょう。
もちろん、「システム開発」をもっと限定して、ITに関わる部分、例えば、プログラムの仕様策定や実行環境の準備、テストや移行計画の策定に限定するのが、IT企業における一般的な解釈です。しかし、ITに関わるかなりの部分は、AI駆動開発やクラウドに代替される事態となり、「システム開発」を狭義な範囲に捉えていては、仕事の機会を失ってしまいます。
「システム開発」の需要は増大する
IT前提の世の中に適応するために、ビジネス・プロセスやビジネス・モデルを作り変えることができなければ、企業は、生き残ることはできなくなりました。この事態に対処するには、狭義のシステム開発の範疇を越えて、本来の意味でのシステム開発、すなわち、「ビジネス上の課題をあきらかにして、これを解決するための仕組みを作る一連のプロセス」への需要が増大します。
もちろんこの状況に対処するには、狭義のシステム開発の知識やスキルが必要です。ただし、それが、過去の常識に基づくものではなく、これからの常識を前提にしなくてはなりません。つまり、高度経済成長時代の惰性、すなわちウオーターフォール開発や構造化プログラミングの常識を捨て去って、変化が速く予測できない社会に俊敏に対処するための手段、例えば、アジャイル開発やクラウド・ネイティブ、マイクロサービスといった新しい常識を前提に、「ビジネスの仕組みを作る」ことが必要になるわけです。
未来に向かって後ろ向きに進んではいないだろうか
カナダの文明批評家でありメディア研究の先駆者であるマーシャル・マクルーハンは、次のように述べています。
われわれはバックミラーを通して現在を見ており、未来に向かって後ろ向きに進んでいる。
私たち人間は、新しい事態に直面すると、最も近い過去のものごとに執着すると、彼は言っているわけです。
「システム開発」でも同様のことが起こっています。例えば、「ウォーターフォール開発とアジャイル開発では、どちらの生産性が高いのか、どう使い分ければいいのか」や「クラウドとオンプレミスはとのように棲み分けるべきか」、「AI駆動開発には置き換えられないプログラミングは、どういうところなのか」などは、「ウォーターフォール開発」、「オンプレミス」、「人間によるコーディング」という「最も近い過去のものごと」への執着を端的に表していると言えるでしょう。「アジャイル開発」、「クラウド・ネイティブ」、「AI駆動開発によるコーディング」がもはや前提であるとすれば、このような疑問を持つことなどありません。まさに、「バックミラーを通して現在を見て、未来に向かって後ろ向きに進んでいる」姿そのものです。
これからのエンジニアに求められる3つのスタイル
このような状況は、見方を変えれば、プログラマー(コードを書く人)がエンジニア(ビジネスの仕組みを作る人)に転換する絶好の機会かもしれません。プログラマーのままでは、仕事ができなくなってしまうわけですから、自分の仕事を再定義せざるを得ません。
では、どのように変えればいいのでしょうか。
- ITが分かり、業務が分かり、経営が分かり、これを自分の言葉で語れる教師的エンジニア
- IT前提のビジネス・プロセスを設計し、実践のシナリオを描くことができるデザイナー的エンジニア
- 高度なシステム設計やプログラミング・スキルを駆使できる職人的エンジニア
いずれの道を選ぶかは人それぞれですが、コンピューター科学やソフトウェア工学の知識が土台になければできない仕事です。
本来の意味での「システム開発」のテーマは、尽きることはなく、ますます増えていくでしょう。まさにこの点に於いて、「IT人材不足」は、さらに深刻な事態になるでしょう。SIビジネス、あるいは、ITビジネスのポテンシャルもここにあります。そのための人材を育てる、集めることに注力すべきは言うまでもありません。
未来を予習する学びのベクトル
過去の復習ではなく、未来を予習する
これからの学びは、このような視点が、大切になります。コンピューター科学やソフトウェア工学は、未来を学ぶ土台です。その土台の上に、過去の常識を当てはめるのではなく、未来の常識を予習して、これからのニーズを先読みする能力を育てなくてはなりません。
昨今、リスキリングという言葉が、世間を賑わしています。リスキリングの前提は、アンラーニングです。アンラーニング(unlearning)とは、学習棄却ともよばれ、持てる知識・スキルのレパートリーのうち有効でなくなったものを捨てることです。その上で、これに変わる新しいことを「リスキリング」することです。「未来を予習する」のは、何をアンラーンすべきかを知るにも必要です。
古いやり方を捨てることができず、過去の成功体験の惰性が残ったままでは、これからの常識が、非常識に写ってしまいます。自ずと自分を正当化するようになり、新しいことへの壁を立ててしまいます。過去の常識を盾に、いまの価値観を持つ人たちを批判し、自分の考えを押しつけてしまう人もいます。当然、新しいことを学ぶことにも消極的になります。そうならないためにも、まずは「アンラーニング」を徹底し、自分の中に凝り固まったバイアスを外さなくてはなりません。
沸き立つエンジニアになるための3つのこと
「学ばない」ことを選択する自由は、もちろんあります。それもひとつの生き方だと思います。しかし、「学ぶ」ことを選択した人たちとの社会的な格差は、当然ながら広がってしまいます。「学ばない」ことを選択することは、この現実を受け入れることでもあります。
もし、これからの時代に求められるエンジニアになりたいのであれば、「会社の必要」に応えることで満足してはいけません。「世の中の必要」に応えることに、価値を求めるべきでしょう。そのためのハードルは、高くありません。例えば、次のようなことをすればいいのです。
- 社外の勉強会やコミュニティに参加して、自分も発言、発表する。
- 仲間と勉強会を立ち上げて、議論やトライアルを楽しむ。
- 面白そう、やってみたいなどのワクワクできるテーマの本を読み漁る、サービスやツールをいじり倒す。
こんな実践が、自分を新しいステージへと引き上げ、どこに行っても必要とされる存在に育ててくれます。まさに、「IT人材不足」の沼の底から沸き立つように、自分の存在を輝かせ、ますます社会にも会社にも必要とされる存在になるはずです。
過去の復習ではなく、未来を予習する
これをひとりでやることは、なかなか大変なことです。ならば、仲間を集め、社外にも関わりを拡げ、志(こころざし)のベクトルが、同じ方向を向いている人たちと、つながることを心がけてはどうでしょう。もちろん、そのための努力は必要ですが、そういう日常が、習慣となれば、これは人生の大きな財産です。
「学ばない日本人」に留まり続けるのか、それとも、「社会に必要とされる存在」へと、自分の居場所を変えるのか、私たちはこの問いに向きあわなくてはなりません。
今年も開催!新入社員のための1日研修・1万円
AI前提の社会となり、DXは再定義を余儀なくされています。アジャイル開発やクラウドネイティブなどのモダンITはもはや前提です。しかし、AIが何かも知らず、DXとデジタル化を区別できず、なぜモダンITなのかがわからないままに、現場に放り出されてしまえば、お客様からの信頼は得られず、自信を無くしてしまいます。
営業のスタイルも、求められるスキルも変わります。AIを武器にできれば、経験が浅くてもお客様に刺さる提案もできるようになります。
本研修では、そんないまのITの常識を踏まえつつ、これからのITプロフェッショナルとしての働き方を学び、これから関わる自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうことを目的としています。
参加費:
- 1万円(税込)/今年社会人となった新入社員と社会人2年目
- 2万円(税込)/上記以外
お客様の話していることが分かる、社内の議論についてゆける、仕事が楽しくなる。そんな自信を手にして下さい。
現場に出て困らないための最新トレンドをわかりやすく解説。 ITに関わる仕事の意義や楽しさ、自分のスキルを磨くためにはどうすればいいのかも考えます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
いずれも同じ内容です。
【第1回】 2025年6月10日(火)
【第2回】 2025年7月10日(木)
【第3回】 2025年8月20日(水)
営業とは何か、ソリューション営業とは何か、どのように実践すればいいのか。そんな、ソリューション営業活動の基本と実践のプロセスをわかりやすく解説。また、現場で困難にぶつかったり、迷ったりしたら立ち返ることができるポイントを、チェック・シートで確認しながら、学びます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
2025年8月27日(水)
AI駆動開発Conference Spring 2025
こんなことやります。私も1枠頂き話をさせて頂きます。よろしければご参加下さい。
【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。