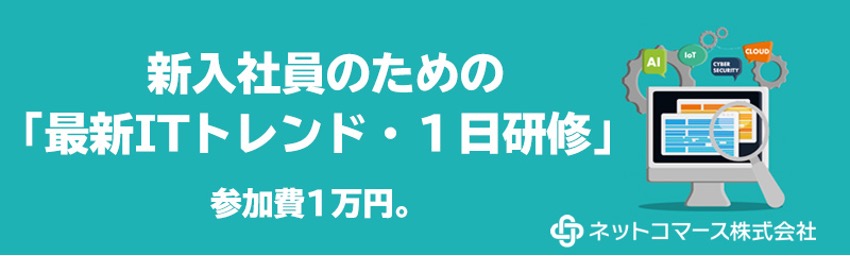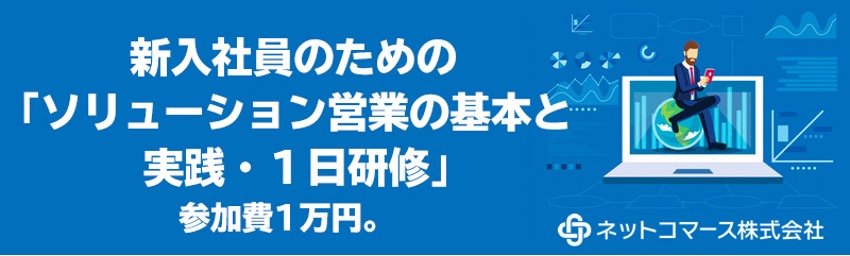インターネットの黎明期から学ぶAI時代の身の処し方
私がIT業界に身を置いた1982年から、既に43年が立ちました。その間で最も大きな変化の節目は、インターネットの登場です。昨日のブログでも述べたとおり、1995年、つまり私が日本IBMを退職したその年が、そんなインターネットの最大のターニングポイントであったことは間違えありません。それは、言うまでもなくWindows95とInternet Explorerの登場です。
インターネットは、通信の民主化を目指した技術ではありましたが、1990年に商用利用が始まった当初、それ使えるのは専門知識を持った一部の人たちに限られていました。それが、1995年のWindows95とInternet Explorerの登場によって、誰もが使えるものへと変わり、真の意味でグローバルコミュニケーションの民主化が始まったのです。
この変化を象徴する言葉として、「IT(Information Technology)」の登場があります。1990年代の後半頃までは、「コンピューター/Computer」という言葉は使われていても、「IT」はほとんど使われることはありませんでした。それがインターネットの普及とともに、一気に「IT」が普及したと言ってもいいでしょう。
そもそも、ITという言葉は、1958年にハーバード・ビジネス・レビューに掲載された論文で、Harold J. Leavitt and Thomas L. Whislerによって初めて使われました。日本では、2000年に「IT革命」が新語・流行語大賞に選ばれるなど、一般的に広く知られるようになりました。このあたりから、「コンピューターという計算機械」は、「コンピュータとインターネットの融合による情報処理・活用のための技術=IT」という大きな枠組みの中の1つの要素に格下げされました。結果として、「ITの民主化」、すなわち誰もが身近にITを使う時代へと移行したわけです。2007年のiPhoneの登場によりスマートフォンという「常時インターネット接続×携帯可能」なコンピューターの登場で、この「ITの民主化」は一層推し進められました。
インターネットをきっかけとしたITの民主化のトレンドは、いまのAIのトレンドととてもよく似ています。ふり返れば、AIの研究が学問分野として確立したのは、1956年夏に開催されたダートマス大学での会議がきっかけでした。ただ、AIを支えるITがまだ黎明期であり、大きな成果をあげることなく40年以上を経過します。
2000年頃、まさにインターネットの普及期であり、IT革命という言葉が登場したこの時期、コンピューターの性能の向上と相まって「機械学習」が主流になり始めました。2006年、トロント大学・教授のGeoffrey Hintonの論文が土台となった機械学習のアルゴリズムであるディープラーニングは、2012年の画像認識コンテストで2位を圧倒的な差で打ち負かし、一気に注目を浴びました。同じ年、Googleは、「人が教えることなく、AIが自発的に猫を認識することに成功した」と発表しました。丁度この頃、GPUについての技術革新があり、高速計算が可能なコンピューターが登場したことで、ディープラーニングは機械学習の主流に躍り出て、いまもその地位を維持し続けています。
ただ、当時のAIは専門家にしか扱えない技術でした。ですから、一般に広く理解されることはなく、その適応も限定されていました。この状況を大きく変えるきっかけとなったのが、2022年11月に登場したChatGPTです。
これまで「専門家にしかあつかえなかった技術」を、日常の言葉で"相談"すれば必要な情報や最適な答えを返してくれるサービスが突如として世の中に登場したのです。これをきっかけにAIへの関心は一気に高まり、その勢いを得て様々なサービスが登場して、AIに関連した製品やサービスの機能・性能は向上し、短期間のうちに適応範囲が拡大していることは、皆さんもご存知の通りです。「AIの民主化」が始まったとも言えるでしょう。企業の中期経営計画や国の研究開発ロードマップに「AIの利活用」が当たり前のように組み込まれるほど、この"AIの民主化"が不可逆的に進みはじめ、AI前提のビジネスを模索する動きが急速に広がっています。
インターネットを民主化し、さらには「ITの民主化」のさきがけとなった「Windows95とInternet Explore」と同様に「ChatGPT」は「AIの民主化」のきっかけを作ったと言えます。
GoogleでAIの開発をリードし、AIの技術発展が「シンギュラリティ」をもたらすと説いたレイ・カーツワイルは、新著『シンギュラリティはより近く: 人類がAIと融合するとき」(NHK出版 、2024年11月)の中で、「収穫加速の法則」について触れています。
「収穫加速の法則」とは、重要な発明は他の発明と結び付き、次の重要な発明の登場までの期間を短縮し、イノベーションの速度は指数関数的に進歩するという経験則のことです。かつてのインターネット黎明期と、いまのAI界隈に起きていることは、まさにこの法則に一致します。
そんな時代にもかかわらず、いまだにAIから一歩離れたところに身を置いている人たちがいます。残念なことですが、IT業界、特にSIerの人たちにもこのような人たちが一定数いることです。その理由は、「ハルシネーションがあるから使えない」「人間がやった方が正確で早い」「難しそうだから使わない」などいろいろとありますが、もはやそんなことを行っているときではありません。たぶんそういう人たちの多くは、しっかりと使い込んではいないのでしょう。ChatGPTが登場して2年半が経ち、当初の状況がどれほど大きく変わってしまったのかを実感できていないのだと思います。インターネットが登場した当初も「インターネットはビジネスでは使えない」と多くの人たちが行っていたこととよく似ています。
いま私たちは、歴史の転換点を立ち、その変化をリアルタイムに目撃しています。これを冷静に捉えれば、かつてインターネットが社会の有り様を大きく変えてしまったように、AIが同様の変化の初期段階にあることは明らかです。ただし、変化のスピードはインターネットの時代よりも加速しているように感じます。
ではどうすればいいのかです。答えは、とても簡単です。
「使いながら考える」
インターネットもまた、そういう人たちがイニシャティブをとってきました。そして、ビジネスや社会を変えてきたのです。そんな歴史から学ぶべきではないでしょうか。
今年も開催!新入社員のための1日研修・1万円
AI前提の社会となり、DXは再定義を余儀なくされています。アジャイル開発やクラウドネイティブなどのモダンITはもはや前提です。しかし、AIが何かも知らず、DXとデジタル化を区別できず、なぜモダンITなのかがわからないままに、現場に放り出されてしまえば、お客様からの信頼は得られず、自信を無くしてしまいます。
営業のスタイルも、求められるスキルも変わります。AIを武器にできれば、経験が浅くてもお客様に刺さる提案もできるようになります。
本研修では、そんないまのITの常識を踏まえつつ、これからのITプロフェッショナルとしての働き方を学び、これから関わる自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうことを目的としています。
参加費:
- 1万円(税込)/今年社会人となった新入社員と社会人2年目
- 2万円(税込)/上記以外
お客様の話していることが分かる、社内の議論についてゆける、仕事が楽しくなる。そんな自信を手にして下さい。
現場に出て困らないための最新トレンドをわかりやすく解説。 ITに関わる仕事の意義や楽しさ、自分のスキルを磨くためにはどうすればいいのかも考えます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
いずれも同じ内容です。
【第1回】 2025年6月10日(火)
【第2回】 2025年7月10日(木)
【第3回】 2025年8月20日(水)
営業とは何か、ソリューション営業とは何か、どのように実践すればいいのか。そんな、ソリューション営業活動の基本と実践のプロセスをわかりやすく解説。また、現場で困難にぶつかったり、迷ったりしたら立ち返ることができるポイントを、チェック・シートで確認しながら、学びます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
2025年8月27日(水)
AI駆動開発Conference Spring 2025
こんなことやります。私も1枠頂き話をさせて頂きます。よろしければご参加下さい。
【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。