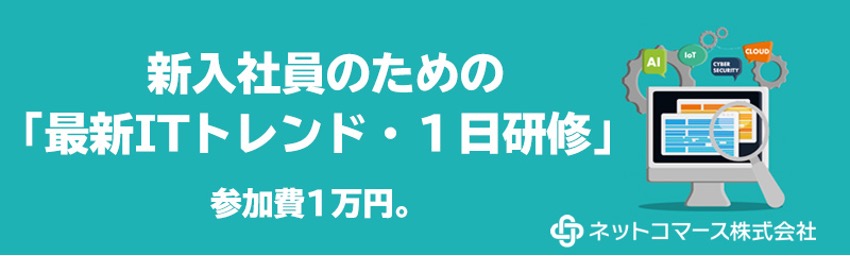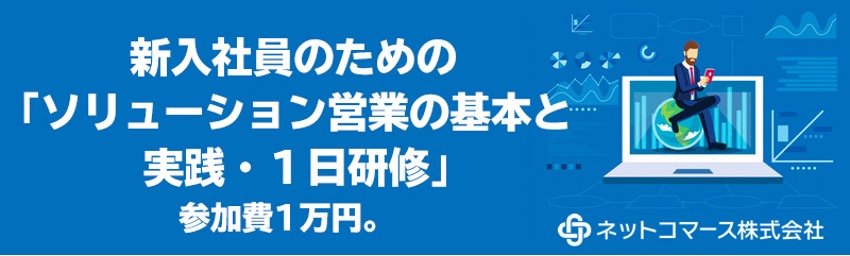若い人たちはオッサンたちを蹴散らして前へ進め!
1995年3月、オウム真理教の地下鉄サリン事件で世間が大騒ぎの時にサラリーマンを卒業し、一人で仕事を始めることになりました。当時はまだインターネットがさほど認知されていない時代でしたが、OS2のPCにTCP/IP接続のためのソフトウェアを自分で導入し、ダイヤルアップ通信で、Netscape Navigatorを使ってホームページを見るということを始めていました。
その年の8月、Windows95が登場し、TCP/IPを標準でサポートしたたこと、そして、ブラウザInternet Explorerも装備され、インターネットへの接続が、格段に簡単になりました。また、ISPが急増し、料金の低廉化が一気に進み、インターネット普及への弾みが付いたターニングポイントとも言うべき年だったように思います。
私は、これは凄いと思い、これで何かビジネスが始められるのではと、自分が始めたアウトドアショップのホームページを作り、オンラインショップも始めました。ただ、インターネット利用者の人口は100万人程度で、その多くは電子メールを利用する人たちでした。また、オンライン決済の仕組みなどなく、それが売上につながることはありませんでした。ただ、その経験を活かして、ホームページの制作やインターネットを使ったプロモーションを手伝う仕事を始め、いま思えば、大手企業のホームベヘージ制作にも関わることとなりました。
アウトドアショップは儲からないため半年ほどで店を閉めましたが、こちらはそれなりに仕事になっていました。また、「ビジネスにインターネットをどう活かせば良いのか」といったことを教える講演を開催し、そこそこ人が集まり、それをきっかけに仕事を頂くこともできるようになりました。
2022年11月にChatGPTが登場し、すぐに使い始め、やはりこれは凄いとなって、早速、「ビジネスに生成AIをどう活かせば良いのか」の話を講義や講演で始めましたが、思い返せば相変わらず同じようなことをやっているなぁと思います(笑)。ほんと、進歩がありませんね。
インターネットが登場した当時、ビジネスに使えるかどうかと言うことについては、多くが懐疑的であったように思います。「ホームページという電子ポスターには使えるが、他には何に使えるんだ?」という雰囲気で、少なくとも私のまわりの企業関係者は、それほどの大騒ぎはしていなかったように思います。そんな中で、私は、「インターネットは凄い!」と、あることないこと(笑)蕩々と語り、夢を売って仕事につなげていたように思います。まあ、そんな「あることないこと」が、いまや当たり前になり、その時には想像もできなかったようなことがどんどんと実現したのは言うまでもありません。
いまふり返れば、当時の私のまわりの企業関係者は「安い通信手段」としてインターネットを捉えていたように思います。確かに、専用線の高価な時代でしたので、「品質は劣るが安く使える」という価値は認識されていたように思います。私のうろ覚えですが、当時の専用線は、10km以内で9万8千円/月だったように思います。それが、距離に関係なく数千円/月で使えるわけで当然と言えば当然です。
ただ、これはあくまで「いまの通信手段を補完する」という視点での見方です。安くなった結果として、新しい経済や社会の基盤、すなわち「サイバー社会」が登場するという発想は、あまりなかったように思います。安い通信手段、安い電子ポスターという、既存の常識の枠組みの中で、インターネットを受け止めていたわけです。
GAFAMなどのBig Tech創業者たちは、日本の多くの企業と異なり、来るべき未来の可能性をイメージし、それを実現しようと自ら動きを始めていました。既存の常識を越える/壊すことを彼ら自身が始めようとしていたわけです。ひと言で言えば「開拓者精神」があったのでしょう。失敗することを積極的に許容し、既存を破壊し新しく作り変える「変革/Transformation」を当たり前に受け入れていたのだと思います。
一方日本の多くの企業は、失敗は恥であり、汚点であるという意識が根強く、「既存を護持し、和をもって貴しとなす」といった価値観の中で、新しいテクノロジーをどのように使っていこうかと考えていたわけです。つまり、現状を維持しつつも、よりよいものに変えていく「改善/Improvement」手段として捉えていたのかも知れません。
その結果は、言うまでもありません。日本は残念ながらいまやIT後進国になってしまいました。後進国というのは言い過ぎだとお考えの方もいらっしゃるとは思いますが、現実を考えれば、日本にITでBig Techに互する企業はありません。
かつての日本は、決してそうではありませんでした。例えば、日本製鉄は、1960年代からメインフレームシステムを利用し、業務・製造プロセスをITで支えてきました。これは、世界にはない最先端のシステムでした。また、1964年、東海道新幹線が運行を始めたときに鉄道の座席予約システムが稼動し、大規模なオンラインリアルタイムシステムのさきがけとなりました。また、新幹線運行管理システム(COMTRAC)は、世界初のPTC(Positive Train Control)システムとして、列車運行を自動で監視・制御するものでした。このような歴史をふり返れば、決して日本の企業文化の中に開拓者精神がなかったわけではありません。
うまくいきすぎて、これを変えたくないという想いが、新しいことへのチャレンジ精神を萎縮させてしまったのでしょうか。そのあたりについては、多くの人たちが既に語っていることでもあり、ここではこの程度に留めておきたいと思います。
いまの生成AIの現状を考えると、かつてのインターネット黎明の現状と、とてもよく似ているように思います。固いというか、奥手というか、生成AIを既存の「改善/Improvement」の手段として受け止めている企業が圧倒的です。かつてと違うとすれば、インターネットの普及により、私のような悪態をつく人たちが沢山いて、それが広まりやすい環境にあること、また、アメリカほどではないものの開拓精神旺盛な若い人たちが、この時代の変化に挑んで、世界を視野に新しいことを始めようとしていることかもしれません。
言い古された言葉ですが、時代は巡ります。ただ、かつての歴史を思い起こし、同じ轍を踏まないようにすることです。一番大切なことは、「オッサンたちが若者たちの足を引っ張らないこと」です。若い人たちには、「そんなオッサンたちを蹴散らして前へ進め!」と申し上げたい。心よりそう願っています。
今年も開催!新入社員のための1日研修・1万円
AI前提の社会となり、DXは再定義を余儀なくされています。アジャイル開発やクラウドネイティブなどのモダンITはもはや前提です。しかし、AIが何かも知らず、DXとデジタル化を区別できず、なぜモダンITなのかがわからないままに、現場に放り出されてしまえば、お客様からの信頼は得られず、自信を無くしてしまいます。
営業のスタイルも、求められるスキルも変わります。AIを武器にできれば、経験が浅くてもお客様に刺さる提案もできるようになります。
本研修では、そんないまのITの常識を踏まえつつ、これからのITプロフェッショナルとしての働き方を学び、これから関わる自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうことを目的としています。
参加費:
- 1万円(税込)/今年社会人となった新入社員と社会人2年目
- 2万円(税込)/上記以外
お客様の話していることが分かる、社内の議論についてゆける、仕事が楽しくなる。そんな自信を手にして下さい。
現場に出て困らないための最新トレンドをわかりやすく解説。 ITに関わる仕事の意義や楽しさ、自分のスキルを磨くためにはどうすればいいのかも考えます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
いずれも同じ内容です。
【第1回】 2025年6月10日(火)
【第2回】 2025年7月10日(木)
【第3回】 2025年8月20日(水)
営業とは何か、ソリューション営業とは何か、どのように実践すればいいのか。そんな、ソリューション営業活動の基本と実践のプロセスをわかりやすく解説。また、現場で困難にぶつかったり、迷ったりしたら立ち返ることができるポイントを、チェック・シートで確認しながら、学びます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
2025年8月27日(水)
AI駆動開発Conference Spring 2025
こんなことやります。私も1枠頂き話をさせて頂きます。よろしければご参加下さい。
【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。