| « 2006年1月14日 | 2006年1月17日の投稿 |
2006年1月23日 » |
てらださんが、オブジェクト倶楽部のクリスマスイベントでライトニングにトークした、エンジアの生きがいに関する考察をまとめた。
「技術屋生活の会計学~going concern な engineering life のために ~」
http://www.geocities.co.jp/u_1roh/columns/going_concern.html
エンジニア生活にとっての、価値とは何か、資産とは何か、について考えさせられる。エンジニアは、自分の資産を都度清算するわけではなく、継続価値(going concern value)として評価しなくてはならない。
普通は「仕事に時間を奪われる」と考えがちです.しかし,このモデルでは「仕事を請けることで時間を得る」という考え方になっています.
こう考えることで、自分の価値を高めていこう、というのが趣旨になっている。すばらしい。
先のエントリで触れた倉貫さんにしても、てらださんにしても、今では旧友の部類になってしまったが、同時代感を共有できているのがうれしい。XPを初めとする新しい開発モデルを実践していく中で、他の分野や価値観に触れ、自分自身で新しい視点を提示できる人はすごいと思う。そのような人たちとこの業界にいっしょにいれて、業界の次を作れる気になった。
倉貫さん(XPJUG会長)のエントリより。
http://d.hatena.ne.jp/kuranuki/20060116/p1
現在の日本のSI業界に潜んでいる問題点を痛いくらい指摘している。現在のやり方では、優秀なエンジニアがやりがいをもって技術を磨き、かつ、よい品質のものを顧客満足高く提供しよう、という構図を作るのが非常に難しい。提供側と顧客側がWin-Winのゴールを持った契約、それを確認しながら進める開発プロセスがないと、日本のSI業界の袋小路から先に進めないのではないかと真剣に思う。また、人の問題に視点を移すと、プロジェクトの成功とエンジニアの仕事質(QoEL)を両立していくことは、少子高齢化や2007年問題、若いエンジアの価値観の多様化から、この業界の人材不足打開と継続可能性(sustainability)とも絡んで、中心課題のように思える。
引用:
そこで、システムを必要としている企業であれば、もはや、SIerなどに頼むのではなく自社で優秀なプログラマーを雇用して、そこで開発をした方が良いのではないだろうか。その方が、コストも安くてすむし、何より、柔軟なシステム開発が可能となる。
一つは上記のようなインソース化の流れが強まるだろう。これは、企業内に開発をもつことで、ゴールのWin-Win化が図れる点、エンジニアが長期視点で成長できる点が良い点だ。
情報システムのユーザ企業において、情報システム自体が「戦略的な価値」である場合(例:Amazon)、もしくは、「オペレーションのインフラ」である場合(例:金融)、情報システムをインソース化することが、1つの解決法として最も具体的で実現性のあるものだと思える。
| « 2006年1月14日 | 2006年1月17日の投稿 |
2006年1月23日 » |
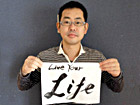
 顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立
顧客に“ワォ!”という体験を提供――ザッポスに学ぶ企業文化の確立 ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う
ちょっとした対話が成長を助ける――上司と部下が話すとき互いに学び合う 悩んだときの、自己啓発書の触れ方
悩んだときの、自己啓発書の触れ方 考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か
考えるべきは得意なものは何かではなく、お客さまが高く評価するものは何か なんて素敵にフェイスブック
なんて素敵にフェイスブック 部下を叱る2つのポイント
部下を叱る2つのポイント 第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命
第6回 幸せの創造こそ、ビジネスの使命