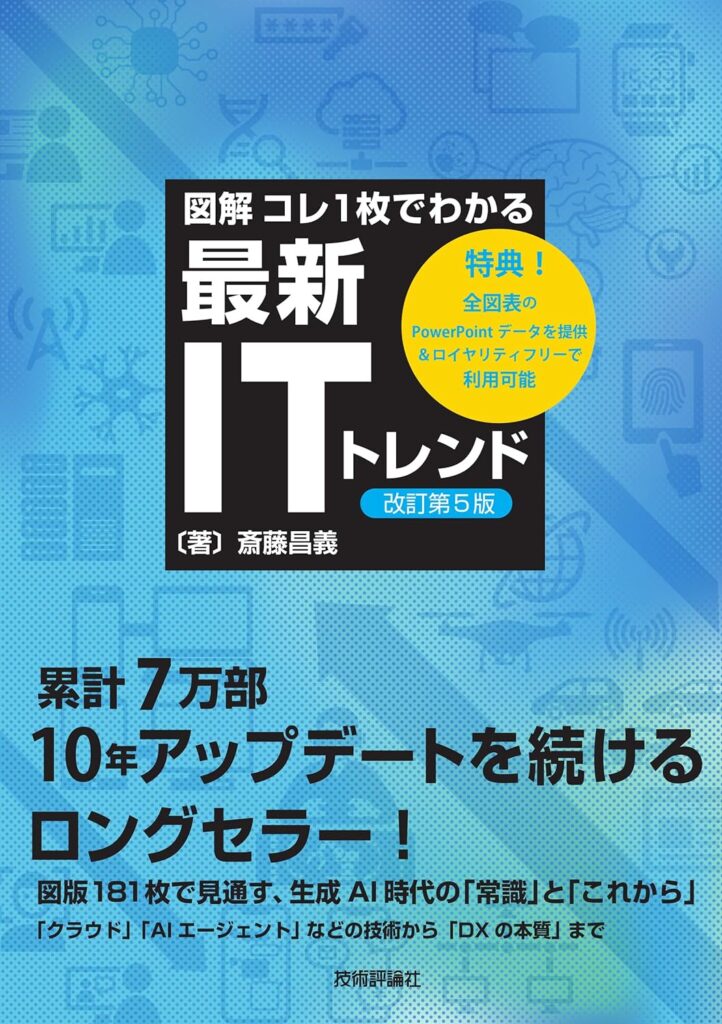「失敗を許さない」文化の代償
昨日のブログでは、過去の成功体験や資産を守ろうとする心理が、変革へのブレーキになることを見ました。しかし、日本において「変革」がこれほどまでに難しい理由は、個人の心理だけではありません。 私たちを取り巻く社会的な「構造」や「空気」そのものが、変革者を許さない仕組みになっているのです。
「出る杭」になることを恐れる心理的ブロック
「出る杭は打たれる」。このことわざほど、日本の組織文化を的確に表している言葉はありません。 新しいことを始めようとする人、異質な意見を述べる人は、組織の調和を乱す存在として、しばしば排除の対象となります。 社会人類学者の中根千枝氏は、その著書『タテ社会の人間関係』の中で、日本の社会構造を「場」の共有による集団意識の強さとして分析しました。そこでは、能力や個人の資質よりも、「ウチ(内部)」の人間であること、そして序列(タテ関係)を守ることが何よりも優先されます。
「『能力』による序列よりも『場』による序列が優先し、個人の資格よりも集団の枠組みが優先するという構成原理は、日本社会のあらゆる集団に浸透している」 (中根千枝『タテ社会の人間関係』より)
このような社会では、AIを活用して個人の生産性を飛躍的に高めたり、既存の序列を無視して新しい提案をしたりすることは、極めてリスクの高い行為となります。たとえそれが論理的に正しいことであっても、「和を乱す」という理由だけで潰されてしまうからです。
さらに、この構造を補強しているのが、評論家の山本七平氏が指摘した「空気」という目に見えない拘束力です。 山本氏は『「空気」の研究』において、日本社会では論理的判断(ロゴス)よりも、その場を支配する「空気(臨在感的把握)」が絶対的な決定権を持つと論じました。 日本文化の根底には、「不立文字(言葉では本質を表現しきれない)」という思想や、あらゆるものに移ろいゆく神性が宿るという感覚があります。これは、「文脈(コンテクスト)」を何よりも重視するハイコンテクストな文化を生みました。 そこでは、「論理的に正しいかどうか」よりも、「みんながどう感じているか」「その場の空気を読んでいるか」が優先されます。
この「空気」の正体は、強固な同調圧力です。 AI時代に変革を起こそうとすれば、当然、これまでの慣習や前例を否定することになります。しかし、どれだけAIが弾き出した「正解」が論理的に正しくても、それが職場の「空気」に合わなければ、実行されることはありません。 「理屈はわかるけど、なんとなく受け入れられない」「時期尚早ではないか」といった、実体のない「空気」によって、変革の芽は摘み取られてしまうのです。
この「出る杭になりたくない」「空気を壊したくない」という心理的ブロックこそが、私たちが新しい地図を描く手を止めてしまう最大の要因の一つです。
正解を探す教育が生んだ「変革アレルギー」
もう一つ、私たちの思考を縛り付けている強力な呪縛があります。それは、「どこかに正解があるはずだ」と信じ込む「正解主義」です。
日本の教育は長らく、与えられた問いに対して、唯一の正解をいかに早く正確に答えるかを訓練してきました。この能力は、欧米の先進モデルという「正解」をいち早く取り入れ、効率的に生産することが求められたキャッチアップ(追いつけ追い越せ)の時代には、極めて有効でした。
しかし、この成功体験が、今の私たちを苦しめています。
「失われた30年」と呼ばれる停滞期、多くの日本企業は現状を打破するために、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)やERP(統合基幹業務システム)、あるいは「デザイン思考」や「アジャイル開発」といった、欧米由来の新しい手法を次々と導入しました。 彼らはこれらを、導入さえすれば会社を変えてくれる「魔法の杖(正解)」だと思ったのです。
しかし、その実態は「正解探し」の延長に過ぎませんでした。 例えば、BPRの本質は業務プロセスをゼロベースで見直し、顧客価値のために再設計することであり、ERPはそのためのベストプラクティスを内包したツールでした。本来であれば、ERPという「正解(世界標準のプロセス)」に自社の業務を合わせるべきでした。 ところが、多くの日本企業は真逆の行動をとりました。「現場のやり方(これまでの自社の正解)は変えられない」と固執し、ERPというパッケージソフトの方を、自社の旧態依然とした業務に合わせて大規模にカスタマイズしたのです。
その結果はどうなったでしょうか。 本来ならばパッケージのライセンス費用で済むはずが、膨大なカスタマイズ費用が発生しました。それだけではありません。ERPがバージョンアップするたびに、独自に改造した部分の手直しや再テストを強いられ、運用コストは雪だるま式に膨れ上がりました。 何より深刻なのは、BPRの本質である「業務変革」が起きず、コストばかりが増大し、本来手に入るはずだった「俊敏性」さえも失ってしまったことです。
彼らは「BPR」や「ERP」という「カタチ(正解)」を手に入れることに必死で、その本質である「自己変革」を置き去りにしたのです。
例えば、「アジャイル開発」の導入もそうです。アジャイル開発とは本来、激しく変化するビジネス環境に対し、自らが主体となって俊敏(アジャイル)に対応するための手段です。そのためには、自社で意思決定を行い、手を動かせる体制(内製化)を整え、必要な人材を育成することが絶対条件となります。 しかし、多くの企業はこの「自ら変わる」という苦痛を避け、「アジャイル開発でやってください」とシステムベンダーに丸投げしてしまいます。これでは、「アジャイル」という言葉を消費しているだけで、構造は旧来の下請け発注と何も変わりません。結果として、本来の目的である「俊敏性」は微塵も得られず、責任の所在が曖昧な失敗プロジェクトが量産されることになります。これは典型的な「手段の目的化」であり、思考停止の産物です。
「デザイン思考」も同様です。これは本来、失敗を積極的に許容しつつ、新しいことを実行に移して、それが正しいかをいち早く検証し、正解を自ら創り出していこうという企業文化があればこそ成り立つ手法です。それを変えることなく、ただ研修を受けさせて手法だけを学ばせても、成果はあげられません。「失敗は許されない」という文化の中で、失敗を前提とした手法を実践しようとすることは、ブレーキを踏みながらアクセルを踏むようなものだからです。
この「正解がないと動けない」「形だけ真似て安心する」という体質こそが、変化の激しい時代における致命的なアレルギー反応、「変革アレルギー」の正体です。
そして今、この「変革アレルギー」はDXやAIの分野でも同じように繰り返されようとしています。 「DXを推進しろ」「AIを導入しろ」という号令のもと、多くの企業がまたしても「正解(成功事例)」を探し求めています。 「他社はどんなツールを使っているのか?」「失敗しない導入方法は?」 そうやって横並びで安心できる「カタチ」を探し、ツールを導入しただけで「DX完了」としてしまう。中身の業務プロセスや組織文化は何も変わっていないにもかかわらずです。 これは、BPRで犯した過ちの再生産に他なりません。AIという強力なエンジンを手に入れても、それを搭載する車体(組織や人のOS)が旧式のままでは、決して本来の性能を発揮することはできないのです。
「失敗」は避けるべきものではなく、投資である
では、この「空気」と「正解主義」の呪縛から抜け出すにはどうすればいいのでしょうか。 そのヒントは、今日のAI時代を牽引するGAFAM(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)などのテック・ジャイアントたちの思考法にあります。
彼らにとって、「失敗」の定義は私たちとは全く異なります。 日本の組織において失敗は「減点」であり、避けるべき汚点です。しかし、彼らにとって失敗とは、「うまくいかない方法を早期に発見するための投資」であり、「成功へのショートカット」なのです。 彼らは「Fail Fast(早く失敗せよ)」を合言葉に、未完成のプロダクトを市場に投入し、ユーザーの反応(データ)を見て、高速で改善を繰り返します。 最初から「正解」が見えているわけではありません。「何が正解かわからない」という前提に立ち、実験と検証を繰り返すことで、自ら正解を創り出していくのです。
このアプローチは、エリック・リースが提唱した「リーン・スタートアップ」という手法そのものです。 リースは著書『リーン・スタートアップ』の中で、「構築(Build)―計測(Measure)―学習(Learn)」というフィードバックループをいかに早く回すかが、不確実な環境で成功するための鍵であると説きました。 完璧な計画(正解)を立ててから動くのではなく、まず最小限の製品(MVP)を作って動く。その結果から学び、次の行動を決める。
「スタートアップの目標は、何を作ればいいのかを、できるだけ速く見つけ出すことだ。(中略)我々が必要としているのは、計画の進捗を報告することではなく、構築・計測・学習のフィードバックループをどれだけ速く回せるかなのだ」 (エリック・リース『リーン・スタートアップ』より)
AI前提の社会は、過去のデータや事例が通用しない「未知の領域」です。 ここでは、誰も正解を持っていません。上司も、経営者も、そしてAIでさえも、未来の正解は知り得ません。 だからこそ、これからの時代に求められるのは、「正解を探す能力」ではなく、「仮説を立て、実践し、失敗から学んで修正する能力」です。
具体的な処方箋:自分だけの「解」を創る4つのステップ
では、正解のない世界で、私たちはどう歩き出せばいいのでしょうか。 答えはシンプルです。「正解」を探すのをやめ、「自分だけの答え」を創り出すことです。 テック・ジャイアントたちが実践している「リーン・スタートアップ」の思想を個人のキャリアに応用し、以下の4つのステップのループを高速で回すこと。これこそが、AI時代の生存戦略です。
ステップ1:情報(素材)を得る 他社事例やAIの知識は「正解」としてではなく、「素材」として取り入れます。「この技術を使えば、自分のこの業務はこう変えられるかもしれない」というヒントとしてストックします。
ステップ2:自分の頭で考える(仮説を立てる) 素材を元に、「自分ならこうする」という仮説を立てます。AIに問いを投げかけ、壁打ち相手として使い倒しながら、自分なりのプランを練り上げます。ここでは完璧さを求める必要はありません。「とりあえず、これでやってみよう」と思えるレベルで十分です。
ステップ3:実行する(小さく試す) 立てた仮説を、できるだけ小さく、早く実行に移します。「会社全体を変える」といった大それたことである必要はありません。「今日の一通のメールの書き方を変えてみる」「AIを使って会議の資料を作ってみる」。 エリック・リースが言うように、「構築・計測・学習のフィードバックループをどれだけ速く回せるか」が勝負です。失敗しても痛手の少ない範囲で、すぐに試すのです。
ステップ4:結果から学ぶ(修正する) やってみた結果、どうだったか。うまくいったなら続ければいいし、失敗したなら「このやり方は違った」という貴重なデータが得られたと考えます。そしてまたステップ1に戻り、次の仮説を立てます。
AI時代において、失敗は「汚点」ではなく、「正解に近づくための投資」です。 「正解」はどこかに落ちているものではなく、この泥臭い試行錯誤のプロセスの果てに、あなた自身の手で創り上げられるものなのです。
「失われた時間」を取り戻すために必要なのは、魔法の杖ではありません。 「正解主義」という重い鎧を脱ぎ捨て、裸一貫で「実験」の荒野へ飛び出す勇気。それだけが、あなたを「変革」へと導くのです。
「システムインテグレーション革命」出版!
AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。
本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。
【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO

8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。