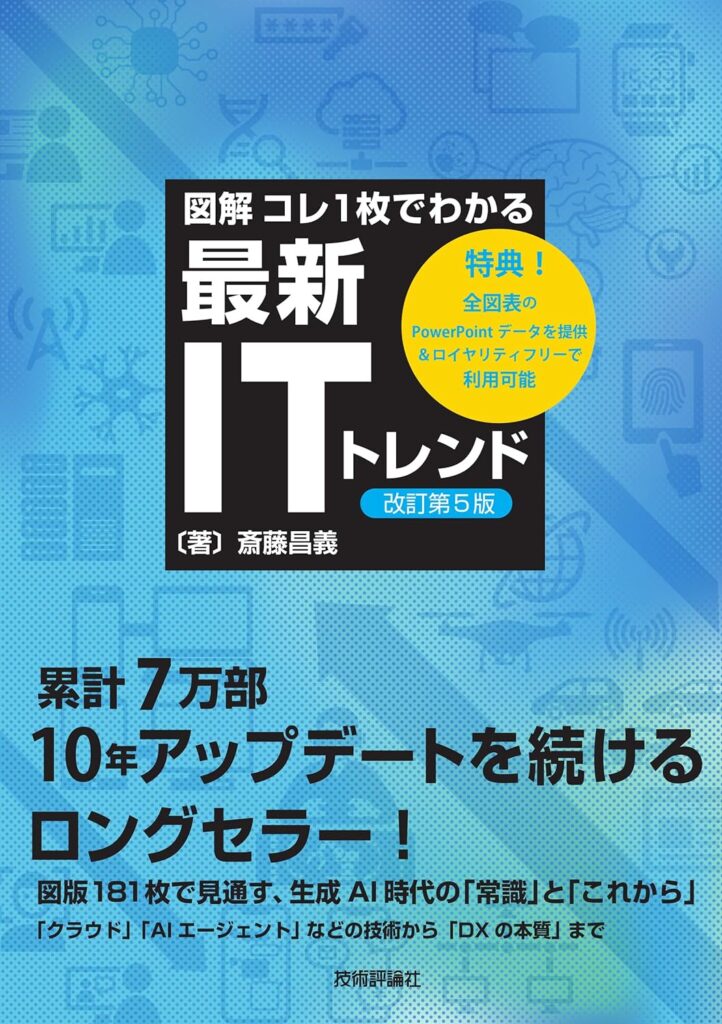あなたは「SI」の本当の意味を知っていますか?歴史から紐解く「ソリューション」と「SI」の本質
そもそも、「SI(システム・インテグレーション)とは何か」を深く考えたことはあるだろうか。その歴史を振り返ることで、SIというサービス・ビジネスの本質、そしてこれから向かうべき先が見えてくる。
ダウンサイジングとマルチベンダーの衝撃
時計の針を少し戻そう。1978年のVAX-11/780の登場はミニコンやオフコンの普及を促し、1981年のIBM PCの出現は、ビジネスにおけるPC利用を一気に拡大させる契機となった。
それまでコンピュータと言えば、高価なメインフレームが主役であり、IBM、富士通、日立といったメーカーに端末からソフトウェアに至る一切合切を任せる「集中システム」が常識だった。しかし、安価な小型コンピュータの台頭により、「何でもメインフレーム」から「適材適所で分散する」ダウンサイジングの流れが加速する。
それに伴い、コンピュータ本体の価格低下と多様化が進み、企業内にはメーカーの異なるコンピュータが混在することになった。いわゆる「マルチベンダー」時代の到来である。これを選んだ企業は、相互接続性や互換性の確保、バージョンアップ、トラブル対応など、膨大な数の分散システムを組み合わせる責任と、運用管理の重い負担を自ら抱え込むことになったのである。
「SI」という概念の誕生
当時、メインフレーム・メーカーの頂点に君臨していたIBMは、当初このダウンサイジングの潮流に抗い、自社製品のみで完結させる「一社完結主義」を貫こうとした。当時IBMの営業として最前線に立っていた私は、その空気を肌で感じていた。
しかし、時代の濁流には抗しきれず、IBMは減収減益に転じ、追い込まれていく。そんな1993年、RJRナビスコのCEOであったルイス・ガースナー氏が招聘された。IBMにとって初の外部出身CEOである。これは、同質化した企業文化のままでは変革の時代を乗り切れないという、IBMの悲壮な決断でもあった。
ガースナー氏は早々にダウンサイジングの現状を直視し、IBMの基本理念であった一社完結主義を放棄した。「メーカーを問わず、その組み合わせに責任を持つ」ことを宣言し、自社製品だけでなく他社製品も含めてシステムの構築やサポートを行う「ソリューション」をサービスとして提供すると決めたのである。そして、このビジネスを「システム・インテグレーション(SI)」と定義した。
この決断について、彼は著書『巨象も踊る(Who Says Elephants Can't Dance?)』の中で、当時のIBM分割論(事業ごとの分社化)を退けた最大の理由として次のように述べている。
「顧客は断片的な技術を求めているのではない。彼らは課題に対する解決策(ソリューション)を求めているのだ。そして、複雑化するマルチベンダー環境において、あらゆる技術を統合(インテグレート)し、責任を持って解決策を提供できるのはIBMだけだ」
それまでも「ソリューション」や「システム・インテグレーション」という言葉は存在したが、明確な定義はなく、各社がキャッチフレーズとして使っているに過ぎなかった。IBMがそこに「統合者としての責任」という新たな魂を吹き込み、ハードウェア・メーカーからサービス・プロバイダーへと大きく軸足を移した瞬間であった。
SIビジネスの本質
このような出自を考えれば、SIというビジネスの本質は自ずと明らかになる。
「お客様のニーズに応えるために、自他にこだわらず製品・サービスの最適な組み合わせを提供し、その実現によって収益を上げる」
この解釈を唯一絶対のものとして押し付けるつもりはない。ただ、自らを「SIer」と任ずるのであれば、そのアイデンティティを明確にし、社会での役割を再認識する必要があるだろう。歴史は、そのための視座を与えてくれる。
「モノ」から「サービス」へ、そしてWeb 2.0へ
もう一つ、ITに期待される役割の変遷を歴史的な視点から見てみよう。
長らくビジネスは「モノが主役」の時代が続いた。ITはその事務処理を合理化する手段、あるいはモノを売るための脇役に過ぎなかった。しかし、1990年代半ばのインターネットの登場と共に変化の兆しが見え始める。IBMがサービス・プロバイダーへ転換したのもこの時期と重なる。
2000年代に入ると、その流れは加速する。当初の一方通行な情報提供から、双方向・対話型の利用へと拡大していく。2005年、ティム・オライリーは「Web 2.0」を提唱した。情報の送り手と受け手が流動化し、誰もが情報を発信できる世界の到来である。梅田望夫氏が著書『ウェブ進化論』(2006年)で指摘したように、ネット上の不特定多数を「能動的な表現者」として巻き込んでいくスタイルが定着し、ブログやソーシャル・メディアが台頭した。
この時代に産声を上げたのが「アジャイル開発」である。2001年の「アジャイルソフトウェア開発宣言」は、ビジネスの主軸がモノからサービスへとシフトし始める時期に登場し、その後、サービス主役時代のITを支える標準的な手法となっていく。
MoT(真実の瞬間)とハイパー・コンペティション
サービスの価値はどこで決まるのか。1980年代、スカンジナビア航空のヤン・カールソンCEOは「MoT : Moment of Truth(真実の瞬間)」という言葉を用いた。
彼は、顧客接点における平均15秒というわずかな時間こそが、企業の成功を左右すると説いた。提供する側と受け取る側の一瞬の関係性が価値を決める。この考え方は、対面サービスだけでなく、インターネットを介したデジタルサービスにおいても真理である。
そして現代、社会は「ハイパー・コンペティション(超競争)」の時代を迎えている。コロンビア大学のリタ・マグレイス教授が『競争優位の終焉』で論じたように、市場の変化に合わせて戦略を動かし続けなければ、競争優位は瞬く間に消滅してしまう。
破壊的な競合の出現、予測不能な市場、めまぐるしく変わる顧客ニーズ。ビジネス・チャンスは一瞬で過ぎ去り、「長期計画でPDCAを回す」といった悠長なやり方では太刀打ちできない。決断と行動の遅れは致命傷となる。
トヨタが自らを「モビリティ・カンパニー」と再定義し、移動をサービスとして提供すると宣言したように、あらゆる産業で「サービスが主役、モノが脇役」への転換が起きている。DX(デジタル・トランスフォーメーション)もまた、この文脈における必然の帰結である。
スピード × アジリティ × スケーラビリティ
このような時代において、ビジネスの価値はMoTの積み重ねで決まる。市場からのフィードバックを即座に受け止め、最適解を判断し、サービスをアップデートし続けなければならない。本番環境への移行と安定稼働が、息をするように行われる必要がある。
必然的に、開発手法はアジャイルでなければならず、それを支えるDevOpsが不可欠となる。ウォーターフォールとアジャイルの違いは、単なる手法の違いではない。「生産物としてのソフトウェア(モノ)」を提供するのか、「サービスとしてのソフトウェア(コト)」を提供するのかという、哲学の違いなのだ。
SIerとしてこれからの戦略を描くなら、この歴史的必然を無視することはできない。
歴史は未来を教えてくれる最高の教師だ。個別の技術の成否までは断言できなくとも、大きな方向性は示してくれる。その目線で現代のテクノロジーを見渡せば、何が「タピオカ(一過性の流行)」で、何が本質的な変革なのかが見えてくるはずだ。
私はいま、これからの時代に求められるキーワードは「スピード × アジリティ × スケーラビリティ」だと捉えている。
これらを実践するための基盤となるのが、アジャイル開発やDevOpsといった「モダンIT」だ。そして、その基盤の上で次世代のテクノロジーがビジネスを加速させる。
例えば、生成AIの台頭は、コード生成や意思決定の支援を通じて「スピード」と「アジリティ」を劇的に向上させる。モダンITで培った土壌があってこそ、この加速装置は真価を発揮するのだ。
また、実用化が迫る量子コンピュータは、従来型のコンピュータでは到達不可能な計算能力を提供し、「スケーラビリティ」の概念を根底から覆すだろう。複雑な最適化問題や新素材探索など、これまで解けなかった課題が解けるようになる時、SIerにはその力を顧客の価値に変換する役割が求められる。
真のインテグレーターへの進化
こうしてSIの本来の意味に立ち返れば、「お客様の要望に応えて、システムを開発する労働力を提供する」という、いわゆる「人月ビジネス」は、決してSIの本質ではないことがわかるはずだ。
生成AIや量子コンピュータといった破壊的なテクノロジー、そしてそれらを高速に実装するモダンITが普及する今、お客様が求めているのは「言われた通りのモノを作る労働力」ではない。これらの新しい時代のテクノロジーを正しく理解し、それをお客様のビジネスの成果にどう結びつけるかを構想し、実現することだ。すなわち、テクノロジーをインテグレーションし、ビジネス成果に貢献することである。
そこに、それが自社のテクノロジーであるかどうかは重要ではない。かつてIBMが自社製品へのこだわりを捨てて顧客の課題解決を優先したように、世界中のあらゆる技術の中から最適解を選び出し、統合して価値を生み出す。それこそが、これからのSIerが目指すべき進化の姿ではないだろうか。
あなたの会社の「SI」は、AIや量子コンピュータ、そしてアジャイルやDevOpsといったモダンITが当たり前となるこれからの社会変化を前提に、アップデートされているだろうか。未だに「モノ作り」の発想や「人月の切り売り」から抜け出せていないとすれば、その未来は閉ざされていると言わざるを得ない。
大切なのは、目に見える現象ではなく、その背後にある本質だ。流行の「DX」や表面的なバズワードで大騒ぎする前に、まずは自らのビジネスの本質が、時代の潮流とAIなどの新たなテクノロジーに正しく適応できているか、問い直すことから始めてはどうだろうか。
「システムインテグレーション革命」出版!
AI前提の世の中になろうとしている今、SIビジネスもまたAI前提に舵を切らなくてはなりません。しかし、どこに向かって、どのように舵を切ればいいのでしょうか。
本書は、「システムインテグレーション崩壊」、「システムインテグレーション再生の戦略」に続く第三弾としてとして。AIの大波を乗り越えるシナリオを描いています。是非、手に取ってご覧下さい。
【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。