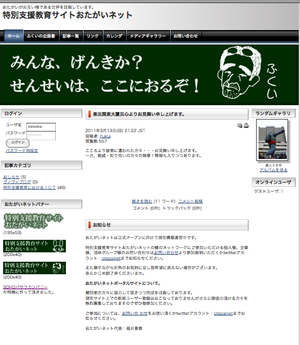SNS活用事例:卒業しても地域や学校とのつながりを! 「おたがいネット」プロジェクト
インターネットのルールを子供にどう教えるか
最近、保護者の方から子どもに教えてほしいという一番多い依頼は「インターネットのルール」。アダルトサイトや2ちゃんねるなどには個人情報などを書かないように、不当請求の詐欺に合わない様にとお子様に教えていらっしゃる方が多いかと思います。
最近はTwitter、mixi、アメーバーピグなどソーシャルネットワークでのトラブルも急増しているようです。これはサービス自体が悪いのではなく、私見では利用する際のリスク・ルールを認識できないままユーザが利用したためにトラブルになるという事例が多いようです。
大人でもTwitterでの発言がもとで炎上した事例は数知れず。はてなブックマークにもいろいろな記事として取り上げられておりました。
▼つぶやきは災いのもと?Twitterが原因で起きた"炎上"騒動 - はてなブックマークニュース
http://b.hatena.ne.jp/articles.touch/201101/2243
大人でも難しいインターネットの使い方。これを子供たちにも分かりやすく教えるにはどうしたらよいのでしょう。そんな時に私が気がついたのがこのSNSです。
▼特別支援教育サイトおたがいネット(ポータルサイト)
おたがいがお互い様である世界を目指しています。
http://otagai.net/
▼おたがいネット(SNS)
http://usagi.otagai.net/
「おたがいネット」さまは特別支援学校に勤務する福井喜章 教諭が学校の生徒の皆様が卒業後も学校や地域とつながりを持てるように立ち上げられたSNSおよびポータルサイトです。
技術者の方がプロボラ(プロの方が専門技術を活かしてボランティアをすること)としてGeeklog(ポータルサイト部分)とオープンソースSNSエンジンMyNETS(SNS部分)で構築されたようです。
「おたがいネット」プロジェクトがすごいと思っているのは以下の点です。
- 特別支援学校に通う子供たちは卒業すると学校や地域から切り離されやすい問題点を解決しようとしていること。
- 特別支援学校に通う子供たちも卒業して就労している大人たちもインターネットを利用する際にネチケットがわかるようにSNSの中のやりとりを通じて経験できる場を提供していること
- 福井先生は特別支援学校の先生をされながらオープンソースを積極的に活用し、ボランティアの協力者の方々とICT教育に取り組んでいること。
参加しているのは福井先生が以前、勤務していた特別支援学校の生徒さん・保護者の方が多いようですが、
- 「SNSでのやりとりはハンドルネームで行うように。」
- 「不用意に日記を外部公開にしない」
など、参加者のみなさまがとまどわないように管理者として先生がほぼ毎日声かけをされているというのは私が気になるポイントです。
福井先生は「SNSはコミュニケーションを確立するツールではなく、コミュニケーションを支援するツールである」とのお考えのもと、子供たちにインターネットのルールを教える取り組みもされていらっしゃいます。
おそらく単に学校の授業や講座で先生がインターネットのルールを説明したとしても、聞いている子供たちも大人も実感がわきにくいのではないかと思います。
しかし、SNSを利用している中で自分が信頼している先生が「個人情報を不用意に日記に書いてはだめですよ」など即時に声を掛けてくれれば、言われた人にとっても実感がわきやすいのではないかと考えました。百聞は一見にしかずなのではないでしょうか。
今年はfacebookが映画や書籍でブレイクしているのでSNSのビジネス利用が注目を集めております。
そのような中、「おたがいネット」プロジェクトのようにSNSを教育にうまく活用できないかと取り組んで成果が出始めているという事例を私は初めて知ったので、大変興味深く感じております。
SNSの特性を「教育」に活かす
「おたがいネット」プロジェクトはSNSの特性を利用することで
- 各地域の方々、協力者・賛同者の方々、在校生・卒業生・保護者、教員・指導員との連携
- OSSの活用
- 地域・教育・行政・医療・福祉の連携
の実現を図られているとのこと。
SNSの運営は「女神様」と呼ばれる管理者以外に場を盛り上げてくれる人が複数でないと継続して何年も運営していくのは難しいものなのですが、福井先生を中心として協力者が徐々に増えてSNSがアクティブになっていっていることがよい意味での驚きでした。
「おたがいネット」さまの場合はリアルな場で知り合っている人たちのSNSだったのが運営が成功している秘訣なのかもしれません。匿名かつ全く見知らぬ人同士でいきなりコミュニケーションを取るというのはかなり高いリテラシーが必要になるのではないでしょうか。
もしTwitterで子供たちもしくは大人が不用意な発言をしてしまい、取り消したいと思ってもフォロワーにとんでしまったツイートを消すことはできません。
インターネットの怖いところは二度と発言を取り消せない、修正できないことがあるという点もあることだと思います。
インターネットのルールを早く理解し、ウェブリテラシーを高めるということはこれからも教育にとって必須事項となっていくのではないでしょうか。
「おたがいネット」プロジェクトは2008年に発足しました。すでにSNS開始から3年が経ったわけですが、福井先生や協力者の方々の取り組みを私自身が子供たちにインターネットのルールを教えるヒントにしたいと感じるSNSです。
IT業界に人ではなく学校の中からもITを積極的に活用していこうという動きが今後どうなっていくのかも2015年デジタル教科書導入とともに注目していきたい点です。
>>「Twitterだけではなくウェブに書き込んだものすべてがバカ発見器なのかもしれない」に続く
追記 2013.3.28 22:50
おたがいネットのサイトの画像を追加しました。改行を増やしました。