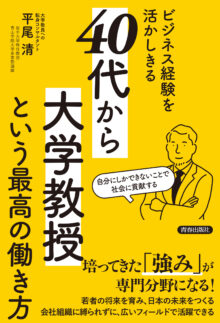「ミドルクライシス」の9割は作られた幻想だ。 煽り情報に流されず、40代・50代が「人生の主導権」を取り戻す方法
「ミドルクライシス」の9割は作られた幻想だ。
煽り情報にダマされず、40代・50代が「人生の主導権」を取り戻す方法
スマホを開くたびに、タイムラインには「おじさんの危機」「中高年の絶望」といった見出しが並びます。 けれども、その"危機"の多くは、現実そのものというよりも、ビジネス上の事情も含めた「情報の演出」によって増幅されたものではないでしょうか。
本稿では、「なぜこんなに危機ばかりが強調されるのか?」という裏側を分解しながら、 条件マッチングの「転職」ではなく、経験を価値に変える「転身」へと視点を移すためのヒントをまとめます。
1.書店もネットも、「おじさん絶望論」であふれている
実際、各種の意識調査を見ても、30代後半〜50代の多くがセカンドキャリアや老後に不安を抱えています。理由として挙げられるのは----
- 将来の生活資金や年金に対する漠然とした不安
- いつまで今の会社で働けるか分からないという不安
- AIやテクノロジーの変化についていけなくなる不安
どれも、「お金」「働き方」「AI」といった、メディアが連日報じているテーマと見事に重なります。 言い換えれば、私たちの不安のかなりの部分は、画面の向こうから流れ込んでくる言葉や映像によって、日々"上書き"されている可能性が高いのかもしれません。
ここで、あなたに問いかけたいことがあります。
あなたが今抱いているその不安は、本当に、あなた自身の内側から自然と湧き出てきたものでしょうか。
それとも、画面の向こう側にいる「誰か」によって、巧みに植え付けられたものではないでしょうか。
2.なぜ「危機」ばかりが叫ばれるのか? その裏側を解剖する
もちろん、人口構造の変化や雇用制度の問題といった構造的課題はたしかに存在します。ただし、情報の「見せ方」には、ビジネス上の事情が色濃く反映されていることも忘れてはいけません。
視点1:危機をあおるほど「商品」が売れる
マーケティングの世界には、「PASONAの法則」という有名なフレームがあります。Problem(問題)を提示し、Agitation(煽り)で不安を増幅させてから、Solution(解決策)として商品やサービスを提示する、という流れです。
つまり、「あなた、このままだと本当に危ないですよ」と感じてもらえなければ、転職サービスも、投資商品も、自己啓発セミナーも、なかなか売れないのです。そこで、問題はしばしば誇張され、「このままでは破綻する中高年」像がくり返し描かれます。
視点2:人間の脳は「悪いニュース」に強く反応する
フランスの思想家ミシェル・ド・モンテーニュは、次のような言葉を残しています(邦訳要約)。
私の人生は恐ろしい不幸に満ちていたが、そのほとんどは実際には起こらなかった。
人間の脳は、生存本能の観点から、ポジティブな情報より「危険信号」に敏感に反応することが知られています。メディアはそれを熟知しており、「40代はこんなに楽しい」という記事より、「40代の悲惨な現実」という記事を量産します。その方が、クリックされやすく、広告もよく見てもらえるからです。
視点3:「おじさんバッシング」は、分かりやすい物語になりやすい
また、「働かないおじさん」「空気の読めない上司」といった図式は、SNS上で共感や怒りを集めやすい"ストーリー"として機能します。その結果、個々の事情や構造的な問題が見えにくくなり、「個人攻撃」と「炎上」が一人歩きしやすくなります。
一方で、同じミドル世代である女性が直面する「ケア責任」や「賃金格差」「キャリアの中断」といった課題は、別の構造的な問題をはらんでいます。本稿では主に「おじさん絶望論」の構図を扱いましたが、女性の視点については、あらためて別の記事で丁寧に取り上げたいと思います。
3.「作られた不安」を見破る:老後2000万円問題と夕張の教訓
「不安を煽る力学」は、キャリアだけでなく、生活全般のテーマにも及びます。象徴的な二つの事例を、あえてざっくりと振り返ってみましょう。

「2000万円」だけが、人生の答えじゃない。
事例1:老後2000万円問題は「一枚の試算表」にすぎなかった
数年前、「老後資金として2000万円不足する」という金融庁の報告書をめぐって、大きな騒ぎが起こりました。報道だけを眺めていると、「2000万円ないと老後は破綻する」というイメージが独り歩きしてしまいます。
しかし実際には、これは家計調査にもとづく「平均的な無職高齢夫婦」の家計モデルから導かれた、ひとつのシナリオにすぎません。その後の調査では、共働きやシニア就労の増加、支出の見直しなどによって家計収支は多様化しており、「2000万円問題」が一律の基準ではないことが指摘されています。
現実には、多くの家庭が「長く働く」「生活をダウンサイジングする」といった工夫の組み合わせによって、自分なりの解を見つけています。それでもなお、「2000万円」という数字だけが切り取られ、見出しとして一人歩きしたことは、私たちがどれだけ「危機の物語」に弱いかを示しているのではないでしょうか。
事例2:夕張市の「医療崩壊」報道と、その後のデータ

「終わり」に見えた地点から、別の選び方が始まることもある。
2007年、財政破綻した北海道夕張市では、市立病院の縮小・再編が大きく報じられ、「医療崩壊」「市民が路頭に迷う」といった言葉が新聞紙面をにぎわせました。
ところが、後年の研究や統計をたどると、必ずしも「悲劇一色」ではなかったことが分かります。住民の側に予防意識が芽生えたり、地域医療のネットワークが再編されたことで、がんや心疾患、肺炎など主要な疾患による死亡率が以前より改善した、という報告も出ています。
もちろん、夕張の人々が味わった不安や不便を軽く扱うことはできません。しかし、「破綻したら終わり」「病院がなくなれば命が危ない」という一方向のストーリーだけでは、現実を正確に捉えられないことも確かです。
共通しているのは、「実は何とかなった」「むしろ良くなった」側面はあまりニュースにならないという点です。安心はクリックを生まず、商品も売れません。その結果、私たちの頭の中には、現実以上に暗い未来像が蓄積されていきがちです。
4.条件マッチングの「転職」から、価値創造の「転身」へ
危機をあおる情報にさらされ続けると、私たちは「今の場所から逃げなければ」と焦りがちです。給料、勤務地、ポジションなど、条件の良さそうな職場を探し、「どこなら今よりましだろうか」と比較し始めます。
もちろん、転職自体が悪いわけではありません。ただ、危機に直面したときに、条件だけを頼りに新しい職場を探すのは、いわば「対処療法」にとどまりやすいという問題があります。状況を十分に整理しないまま環境だけを変えると、数年後に同じパターンで行き詰まってしまうことも少なくありません。
危機管理の基本は、本来とてもシンプルです。
- まず落ち着いて、今起きていることを事実ベースで把握する
- 次に、自分自身の置かれている状況や資源(経験・スキル・人脈)を整理・分析する
- そのうえで、「どの視点から見直すか」を決め、複数の打開策を検討する
このステップを飛ばしてしまうと、金融商品や転職サービスなど、「目の前の不安を一気に解決してくれそうに見える選択肢」だけが、過度に魅力的に見えてしまいます。
だからこそ私は、まず「転職」よりも「転身」という視点に注目してほしいと考えています。 ここで言う「転身」とは、「会社に評価される自分」から一歩離れ、「社会に価値を渡す自分」に生まれ変わることです。
中高年には、これまで培ってきた経験やスキル、人間関係という大きな資産があります。それらをいったん棚卸しし、別の文脈につなぎ直すだけでも、見えてくる可能性は大きく変わります。
- 営業一筋で築いた交渉力を、地域プロジェクトのファシリテーターとして活かす。
- 数多くの失敗プロジェクトの経験を、大学や専門学校で「生きた経営学」として伝える。
マーケターの森岡毅氏は、不安について「本能を克服して挑戦しているときに鳴る、進軍ラッパのようなものだ」と語っています。不安を感じるのは、あなたが弱いからではありません。むしろ、新しいステージに足を踏み入れようとしているサインなのだと私は思います。
損得勘定だけでは測れないところに、人生の醍醐味があります。視点を少し変えるだけで、これまで「重たい荷物」だと思っていた経験が、「誰かの未来を支える宝物」に変わるかもしれません。
5.次回予告:あなたのキャリアの中に眠る「お宝(実践知)」を掘り起こす
ここまで読み進めて、「とはいえ、自分にそんな価値があるだろうか」と感じた方もいるかもしれません。長く同じ業界にいると、むしろ自分の経験の特別さに気づきにくくなってしまうものです。
次回の記事では、あなたのキャリアの中に眠る「実践知」をどのように見つけ出し、言語化し、次のステージにつなげていくかを、具体的なステップとしてご紹介する予定です。
ご興味を持たれた方に。
40代・50代のビジネスパーソンが、これまでの実務経験を「学び」や「教育」、そして地域や次世代の未来づくりへとどうつなげていくか――。
そうした具体的なステップや応募戦略、準備の進め方については、拙著でより詳しくまとめています。
次の一歩を考えるヒントとして、以下の書籍案内もあわせてご覧いただければうれしいです。
関連する拙稿は、ダイヤモンド・オンラインの著者ページからもご覧いただけます。
ダイヤモンド・オンライン 平尾清 記事一覧
どんなスタートラインからでも、未来へ向かうことはできます。作られた危機に振り回されるのではなく、
自分の経験をどう未来に渡していくかを、まわりの人たちともシェアしながら、一緒に考えていければうれしいです。