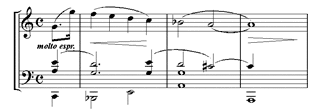昇華か未練か?「死と変容」のラスト50小節
»
以前にもちょっと触れた次の演奏会で取り上げる作品、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「死と変容」は、病の床に伏した芸術家が、発作に苦しんだのち、魂が肉体を離れ天国へ、というストーリーがあり、いわば伊丹映画「大病人」の音楽版といったところだ。
音楽を具体的な情景描画として用い始めた作品として、ベートーヴェンの田園が有名であるが、リヒャルト・シュトラウスに至って、これは完成したと言ってよい。映像がなくとも、音楽が情景を映し出す、映画音楽なんか脱帽の域だ。
とはいえ、細部の感情描写は、映像であっても解釈がいろいろあるように、楽譜に記されただけの音素材をもってしては、規定しようがない。その一部は演奏者に委ねられるのだ。
特に宗教観の違うわれわれが、ドイツ人の宗教観を元につくられた「死」を題材とした作品に向き合うと、ときに違う解釈をすることもある。
ベッドに伏し、苦しみに耐えたのち、ひとときの安らぎに青春時代を思い出し、再び発作、そうして死を迎えるという状況にあるのがラスト100小節。日本的には三途の川へ向かうところか。ここで、成仏するかという前に、未練を見せるのが次のフレーズ。
中盤の青春時代の思い出で、若々しく奏でられたテーマが、厭世的な和声でよみがえってくる。個人的には、この部分、未練というよりすでに達観した境地という感じで演奏していたのだが、指揮者の意見としては、現世への最後の未練だそうだ。
なるほど、この先どこへ向かうかという意識の差もあるのだろう。ちなみに、曲の方は、極めてオーソドックスに天に召されていくクライマックスへと進み、静かに終わる。
SpecialPR