生成AI時代の学校教育はどうあるべきなのか
最近では、セミナーや講演で生成AIについてお話しする機会が増えていますが、先日ある企業様向けの講演で、参加された方から「小学校の子どもがいるのですが、今からスマホや生成AIを与えても良いのでしょうか?」というご質問をいただきました。私は教育の専門家ではありませんが、「私自身、それに対する答えは持っていませんが、時代の流れからして与えないわけにはいかないと思います。ただ同時に、基礎的な国語教育も疎かにはできないでしょう。」とお答えしました。確かにこれは切実な問題ですね。
ChatGPTが公開された直後のブログで、大学などの高等教育の現場で「学生がAIでレポートを書くようになるのでは」という懸念について取り上げましたが、これは大学生など、しっかりとした言語能力を持っているという前提で、生成AIを使って「ズルをする」ことへの懸念でした。しかし先の質問は、初等・中等教育における問題で、「そもそも言語能力が未発達な状況で生成AIを安易に与えるべきなのか。」という懸念です。考えるべきことはたくさんありそうですが、今回は生成AIの主要な機能であり現在の国語教育でも大きな部分を占める「作文力」について考えてみます。
 言語系の生成AIは、文章を作ってくれるAIです。しかも、その精度は劇的に向上しており、今では人間が書いたものかどうかの判別すら難しくなっています。確かに、人間は今後、文章を書「か」なくても良くなるのかも知れません。では、人間は今後、文章を書「け」なくても良いのでしょうか?
言語系の生成AIは、文章を作ってくれるAIです。しかも、その精度は劇的に向上しており、今では人間が書いたものかどうかの判別すら難しくなっています。確かに、人間は今後、文章を書「か」なくても良くなるのかも知れません。では、人間は今後、文章を書「け」なくても良いのでしょうか?
AIの間違いに気づくためには、AI以上の国語力が必要
よく知られるように、生成AIの限界として「ハルシネーション」が挙げられます。これは、生成AIが事実と異なることをあたかも事実であるかのように「自信たっぷりに嘘をついてしまう」現象で、現在の生成AIの仕組上完全に無くすとはできないとされています。なまじ文章が自然なものであるだけに、この嘘を見抜くのはどんどん難しくなっています。そのようなとき、人間側がAIに「騙されない」ようにするためには、AIの出力を鵜呑みにせず、「何かおかしい」と思ったら自分でWebを検索したり書籍にあたるなど、「裏をとる」ことが必要になります。
そのためには、AIが出してくる答えに「違和感を感じる」必要がありますが、これを感じ取るためには、生成AIと同等、あるいはそれを凌ぐ国語力が必要になるのではないでしょうか。今は義務教育や高等教育を終えて、一定水準の国語力を備えた上で生成AIを活用している方が大半だと思いますが、今後生成AIの利用が広がれば、国語力が身についていない初等教育の段階で生成AIに触れることが多くなるはずです。そのときに、有効な活用方法を教えることはもちろん大事ですが、それと同時に国語力(作文力)を高めるための教育も(少なくとも今の状況では)必要なのではないでしょうか。
文部科学省はどう考えているのか
文部科学省も、この件に関してガイドラインの作成に着手しています。
しかし、内容としては教育関係者向けの参考資料という位置づけで、「現場で注意すべきこと」に留まっている印象ですし、国語教育をどうこう、という話では無さそうです。
生成AI自身がまだまだ進化していくでしょうし、何ができ何ができないのかを見極めずに方針を決めるのも難しいでしょうが、それではいつまでも決められないということにもなりかねません。国民的な議論が必要な問題と言えそうです。
【最終案内】ITソリューション塾・第49期(2025年5月14日〜)
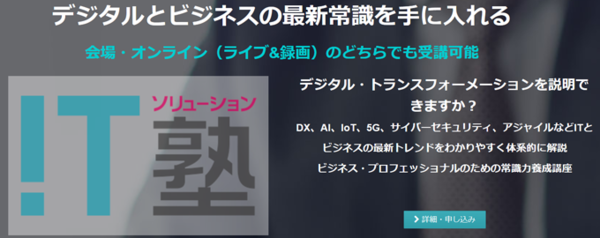 次期ITソリューション塾・第49期(2025年5月14日 開講)の参加者を募集しております。
次期ITソリューション塾・第49期(2025年5月14日 開講)の参加者を募集しております。
ITベンダーにお勤めの方、ユーザー企業でDXやAIに取り組んでいる方向けに、毎週一回、さまざまなトピックを取り上げ、最新のITトレンドについて知識を深めていただきます。また、現在注目されているさまざまな技術が相互にどのように連携しているのか、歴史的な視点を交えて解説することで、技術の本質を理解していただきます。知識を真に内面化するためには、表層的な概念では無く、本質を理解することが重要です。
たとえば、AIサービスを賢く使いこなすためには、AIの仕組みやこれまでの進化の過程を理解することが重要です。そしてそれをビジネスに適用していくためには、AIそのものももちろん重要ですが、Web3やIoT、アジャイル開発/DevOpsといった分野にAIがどのような影響を与えていくのかを、幅広い視点から捉える必要があります。ビジネス環境全体を俯瞰し、各々のテクノロジーがどのように関連し、連携しているかを捉えることで、トレンドを掴むことができるのです。
ITソリューション塾では、最新技術の中身を紹介するだけで無く、他の技術との関わりや歴史的経緯を理解していただくことで、より広い視野の元で最新のトレンドを考えていただけるような講義を目指しています。
- 日程 :初回2025年5月14日(水)~最終回7月23日(水) 毎回18:30~20:30
- 回数 :全10回+特別補講
- 定員 :120名
- 会場 :オンライン(ライブと録画)
- 料金 :¥90,000- (税込み¥99,000) 全期間の参加費と資料・教材を含む
詳細なスケジュールは、こちらです。