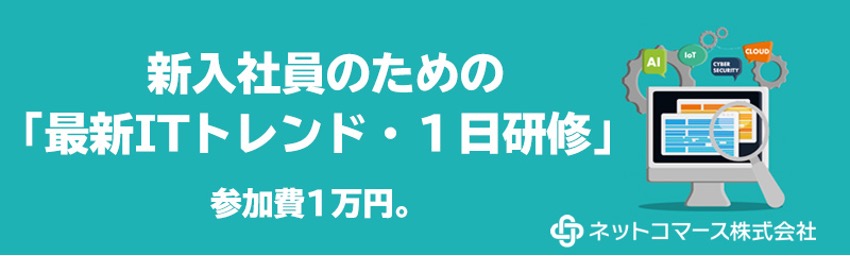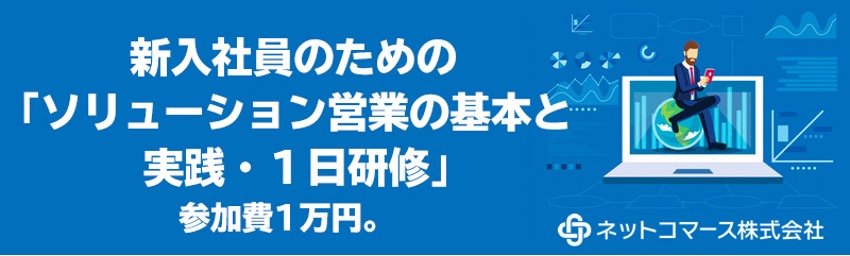「この1年で3人辞めてしまいました」/なぜ優秀な若手は辞めていくのか?
「優秀なエンジニアが、この1年で3人辞めてしまいました。来月もまた一人やめる予定です。いったい、どこに問題があるのでしょうか。」
あるSIerの経営幹部の方からこんな話を伺い、私は次のように答えました。
「仕事が、楽しくないからではないでしょうか?」
この問いへの答えにこそ、多くのSIerが抱える構造的な問題の本質が隠されています。
安定と引き換えに失われた「楽しさ」
かつて企業のIT化を牽引した「守りのIT」投資は一巡し、多くのユーザー企業は膨大なシステム資産を抱えています。その結果、情報システム部門の予算の7〜8割が、既存システムの運用・保守に充てられるようになりました。
この状況は、SIerにとってもビジネスモデルの転換を意味しました。リスクを伴う新規の請負開発よりも、既存システムの保守・運用を継続的に請負う方が、安定した収益を見込めます。結果として、多くのSIerが保守・運用ビジネスへとかじを切りました。
それは、SIerとユーザー企業の双方にとって「楽」な選択でした。開発に携わったエンジニアがそのまま保守を担当すれば、余計な引き継ぎの手間はかかりません。こうして、個々のシステムは特定のエンジニアに依存し、属人化が進みました。この「人とシステムの依存関係」が、皮肉にも長年にわたる顧客との安定的な関係を支えてきたのです。
しかし、その安定は今、静かに崩れ始めています。
忍び寄る3つの危機
長年続いた「安定モデル」は、外部環境の大きな変化によって揺らいでいます。
1. 終わらないコスト削減圧力 「今の仕事内容や品質はそのままに、支払金額を10%下げてほしい。」 顧客からのこのような要求は後を絶ちません。利益率の低い保守・運用ビジネスにおいて、この要求は経営を直接圧迫します。
2. 顧客ビジネスの変化 M&Aや事業再編が活発化する中、既存の基幹システムでは変化に対応しきれず、全面的なシステム刷新に踏み切る顧客が増えています。そうなれば、これまで安定収益源だった「人とシステムの依存関係」はあっけなく断ち切られ、長年の取引実績が次の契約を保証してくれるとは限りません。
3. ユーザー企業の内製化という大きな潮流 そして今、最も大きな構造変化が起きています。それは、ユーザー企業自身が開発力を持つ「内製化」の拡大です。クラウドや優れた開発ツールの登場により、企業はSIerに頼らずとも、自社で迅速にシステムを開発・運用できるようになりました。これにより、SIerの伝統的な下請け構造は根底から覆され、単純な労働力を提供するだけでは価値を生み出せない時代が到来したのです。
新時代への挑戦を阻む「悪循環」
世の中では、AIを活用してビジネスの差別化を図る「攻めのIT」への期待が急速に高まっています。しかし、その主導権は情報システム部門ではなく、事業部門が握ることがほとんどです。旧来の関係性に安住してきたSIerは、この新しいビジネスに関わるきっかけさえ掴めずにいます。
さらに、「AI駆動開発(AI-Driven Development)」の波が、既存のビジネスモデルを根底から揺さぶろうとしています。AIがコードを生成し、テストを自動化するこの新しい開発スタイルは、一見すると生産性を劇的に向上させるチャンスに見えます。しかし、それは同時に深刻な脅威でもあります。今後は、AIツールの活用を前提とした生産性が基準となり、それを元に開発の単金が設定されるようになるでしょう。これは実質的な単価の引き下げ圧力となり、当然ながら利益を圧迫します。結果として、工数提供による収益を前提とした従来のビジネスモデルそのものの維持を困難にするのです。感度の高い若手ほど、この変化を肌で感じ取り、『この会社にいても、市場で通用するスキルは身につかない』と見切りをつけているのです。
経営層は、新しい技術への挑戦が必要だと十分に理解しています。しかし、低い利益率の中で目先の稼働率を維持しなければ、そのための原資さえ確保できない。結果、収益性の不確かな新しい取り組みに人材を割くことができず、変化から取り残されていく。そんな悪循環に陥っているのです。
若手はなぜ、会社を去るのか
この悪循環の最大の犠牲者は、未来を担う若手エンジニアです。
新しい技術を学び、市場価値の高いスキルを身につけたいと願っても、会社が用意する仕事は、レガシーシステムの保守・運用ばかり。彼らの低い単価は会社の貴重な収益源であり、稼働率を上げるための「駒」として扱われがちです。
上司に新しいアイデアを提案しても、「リスクがある」「まだ早い」と諭されるだけ。波風を立てずに会社で生き残ってきた上司たちの処世術は、若者たちの目には「成長の放棄」と映ります。
彼らが感じているのは、単なる不満ではありません。
-
成長の危機: このままでは自分の市場価値が上がらない。
-
生命の危機: 変化に対応できないこの会社に、未来はない。
この本能的な危機感こそが、『楽しくない』という一言に集約されているのです。彼らにとっての『楽しさ』とは、自身の市場価値が高まる『成長実感』に他なりません。そして、まだ未来に多くの選択肢を持つ優秀な若者ほど、「やってられない」と会社を去っていくのです。
「楽しい会社」こそが生き残る
SIerにとって、人材は唯一無二の商品です。高い技術力と高いモチベーションを併せ持った人材こそが、最高の価値を生み出します。それにもかかわらず、その「商品」への投資を怠るのは、研究開発費を削る製造業と同じです。いずれ売るものがなくなるのは自明の理です。
若手社員たちは、決して自分勝手なわけではありません。彼らと話せば、「もっと会社をよくしたい」という熱い想いが伝わってきます。彼らは、世の中が何を求めているかを敏感に感じ取っているのです。
もはや、彼らの声に耳を傾け、信頼して任せるしか道はありません。小さな失敗を許容し、挑戦を称賛する。このささやかな『投資』こそが、会社を生き残らせる唯一のきっかけなのです。
もはや、時短だけの『働き方改革』では意味がありません。企業に今問われているのは、『若者が挑戦を楽しみ、成長を実感できる環境を、いかに戦略的に構築するか』という経営課題そのものなのです。
発想を転換し、これまでのやり方を「変える」のではなく、若手が楽しめる会社を「新たに創る」くらいの覚悟が必要なのかもしれません。
少子高齢化が進み、若手人材の獲得競争はますます激化します。もはや、会社が若者を選ぶ時代は終わり、若者が会社を選ぶ時代となりました。若者に選ばれる会社になることが、いま求められているのです。
この現実から目を背ければ、今日もまた、未来を担うはずだった優秀な人材が、静かにあなたの会社を去っていくでしょう。
今年も開催!新入社員のための1日研修・1万円
AI前提の社会となり、DXは再定義を余儀なくされています。アジャイル開発やクラウドネイティブなどのモダンITはもはや前提です。しかし、AIが何かも知らず、DXとデジタル化を区別できず、なぜモダンITなのかがわからないままに、現場に放り出されてしまえば、お客様からの信頼は得られず、自信を無くしてしまいます。
営業のスタイルも、求められるスキルも変わります。AIを武器にできれば、経験が浅くてもお客様に刺さる提案もできるようになります。
本研修では、そんないまのITの常識を踏まえつつ、これからのITプロフェッショナルとしての働き方を学び、これから関わる自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうことを目的としています。
参加費:
- 1万円(税込)/今年社会人となった新入社員と社会人2年目
- 2万円(税込)/上記以外
お客様の話していることが分かる、社内の議論についてゆける、仕事が楽しくなる。そんな自信を手にして下さい。
現場に出て困らないための最新トレンドをわかりやすく解説。 ITに関わる仕事の意義や楽しさ、自分のスキルを磨くためにはどうすればいいのかも考えます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
いずれも同じ内容です。
【第1回】 2025年6月10日(火) ※受付を終了しました
【第2回】 2025年7月10日(木) ※受付を終了しました
【第3回】 2025年8月20日(水)
営業とは何か、ソリューション営業とは何か、どのように実践すればいいのか。そんな、ソリューション営業活動の基本と実践のプロセスをわかりやすく解説。また、現場で困難にぶつかったり、迷ったりしたら立ち返ることができるポイントを、チェック・シートで確認しながら、学びます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
2025年8月27日(水)
【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。