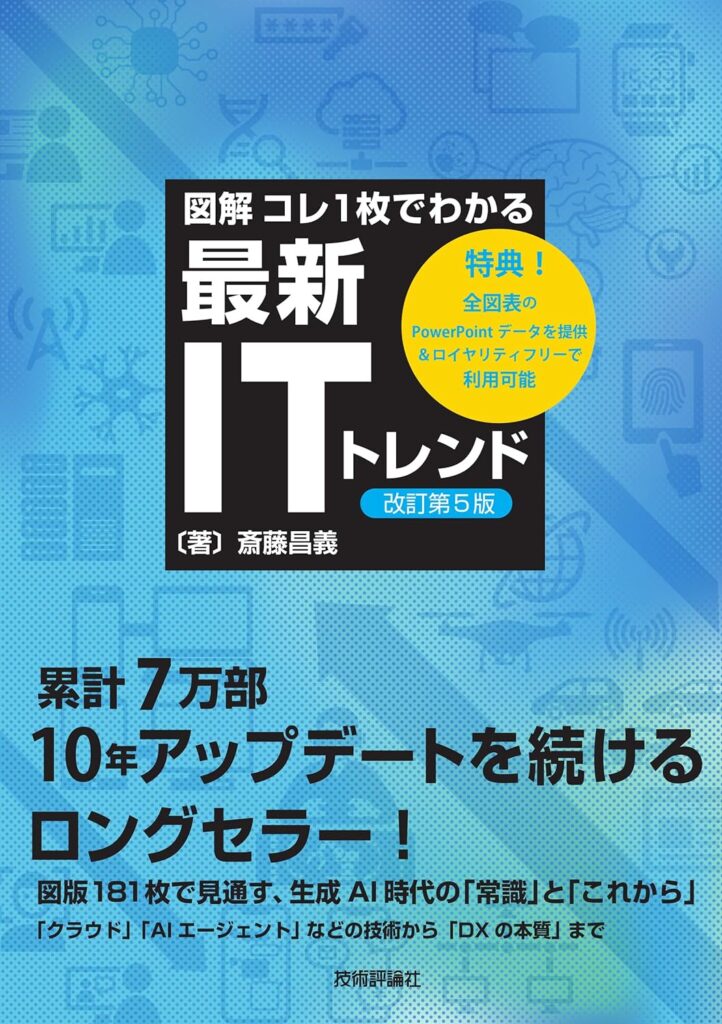「ソフトウェアファースト第2版」から読み解くソフトウェアの基本
「ソフトウェアファースト第2版〜あらゆるビジネスを一変させる最強戦略〜・及川卓也著(日経BP・2024/9/13)」を読み終えたのは、本書が出版されてすぐのことだった。面白くて一気に読んだ。その一方で、エンジニアとしての実務経験がなく、彼が生業としているプロダクト・マネージメントについても、言葉の上でしか理解できていない私にとっては、直感的にピントこないところもあったというのが正直なところだった。
そんなこともあって、所々読み返しながら、「ソフトウェアファースト」の意図するところを解きほぐしながら、自分の言葉に置き換えようと、いまも机の上に置いている。そんな私なりの本書「ソフトウェアファースト」の解釈について、書いてみようと思う。
「ソフトウェアファースト」というより「ソフトウエアの基本」である
彼は、著書の中で、「ソフトウェアファーストとは、ソフトウェアを最初から考えようということであって、ソフトウェアがハードウェアよりも大事ということではありません。」と書いている。この言葉は、本書の中核をなすメッセージだと私は考えているのだが、なんとも遠慮がちだ。もっとはっきりと、その意図を伝えてはどうかと感じた。例えば、次のような表現だ。
「ソフトウェアこそ価値の源泉であり、ハードウェアはソフトウェアの価値を引き出す手段である」
たぶん、日本にまだまだ多い「ハードウェアあってこそのソフトウェアである」と考えるハードウェア優越論者への気遣いとして、このような優しい表現にしているのだと思うのだが、もうそろそろこの真実をストレートに伝えるべきときではないかと私は思う。
現実を見れば分かることだが、多くのハードウェアはソフトウェアなくして動かない。物理的にスイッチやダイヤルを回しても、それは、その動きを検知するセンサーに過ぎず、その動きをソフトウェアで処理して、ハードウェアを動かすことがもはや当たり前の世の中だ。
家電製品、自動車、航空機など、いまや多くのハードウェアはソフトウェアに制御されている。
もちろん、ハードウェアなくして現実世界のものごとやできごとを検知し、作用を及ぼすことはできないわけで、両者は不可分の関係にあることことは言うまでもない。しかし、ハードウェアを使うユーザーは、ハードウェアそのものを手に入れることで満足することはなく、それを使う体験に価値を見出す。その体験は、いまやソフトウェアに主導権が握られている。
体験を向上させることで、私たちの得られる価値は向上するわけだが、それを実装するのはソフトウェアであり、そのソフトウェアの制御の元にハードウェアが機能する。あるいは、体験を向上させるためには、ソフトウェアの機能や性能を向上させなければならないわけで、そのためにはハードウェアもまた機能や性能を向上させるべく、努力が積み重ねられている。
また、ソフトウェアの機能や性能の発展速度は、ハードウェアよりも遥かに早い。この技術発展の速度のギャップを埋めるにもソフトウェアを前提に考えることが、合理的な考え方であろう。
そう考えると、「ソフトウェアあってこそのハードウェアである」とも言えるわけで、「ソフトウェアファースト」の本質は、この点にあると私は考えている。
また、世間では、「データドリブン経営」などと言う言葉が喧伝されている。しかし、「データドリブン経営」で、自分たちは何をどのように変えたいのか、どのような事業成果を生みだしたいかの具体的なイメージを描けている人は少ない。それにもかかわらず、データの収集と管理の方法、あるいはデータを加工するツールの機能や性能に一喜一憂している。
「何をしたいのか、何を解決したいのか」の問いを立て、この問いを解決するために必要なデータを収拾する。そのデータをロジカルに処理できてこそ、問いは解決できる。そのロジックを実行するのがソフトウェアであり、ソフトウェアなくしてデータは、なんらの価値も生みださない。
デジタル化と言う言葉がある。コンピューターでは扱えないアナログなものごとやできごとをセンサーでデジタルデータに置き換える、あるいは、紙やハンコでの事務処理をコンピューターで処理してデジタルデータに置き換えることで、コンピューターが扱えるように変換することをデジタル化という。しかし、データがデジタルになっても、それを適切に処理するプロセスがなければ価値は産み出せない。つまり、ソフトウェアなくして、データは何の役にも立たない。つまり、デジタル化はソフトウェア化と不可分であるということだ。
DXもまた然り。デジタル前提の世の中に適応するために会社や社会の仕組みを新しく作り変えることを言う。そのためには、データもデジタル化も前提となるわけだが、ソフトウェアなくしてこれを実現することはできない。つまり、DXは、社会やビジネスのソフトウェア化である。言葉を変えれば、「ソフトウェア前提で社会やビジセネスを再定義・再構築する」ということであり、「ソフトウェアを最初から考えよう」なんていう、彼の話しの域を超えているように思う。
また、いまや変化の予測できない時代である。「正確に未来を予測して計画通りものごとをすすめていく」ことは、不可能になった。だから、「いまの変化をデータで直ちに捉え、その時々の最適を選択し、継続的に改善する」ことが、事業の継続や企業の存続のためには不可欠だ。後者のような「変化に俊敏に対処できる」能力は、人間やハードウェアに過度に依存しては実現できない。ソフトウェア化は絶対条件である。DXとはそんなソフトウェア化された社会や会社に作り変えること(=変革すること)だとも言える。
つまり、本書は、「ソフトウェアが、いまの世の中で、社会やビジネスにとってどのような役割を果たしているか」を説いた「ソフトウェアの基本」についての書であると言えるのではなかろうか。
プロダクトという考え方の大切さ
本書のもうひとつの中核をなすのが、「プロダクト・マネージメント」だ。プロダクトという言葉から誰もが想像するのは、「工業製品」や「ソフトウェア・パッケージ」などではないだろうか。かく言う私もそんなイメージを描いていた。
彼が本書で説くプロダクトは、それよりも範囲が広い。「顧客に価値を提供し、ビジネス上の対価を得る手段」と言い換えることができるだろう。例えば、マッサージはサービスを受ける人へ快楽という価値を提供し、サービス提供者に収益を提供するプロダクトであるといえる。
この一連のプロセスを確実かつ効果的に実現するために管理することが、「プロダクト・マネージメント」だ。こちらについては、及川さんの著書「プロダクトマネジメントのすべて」に詳しいので、ここでは、この程度に留めておく。
彼の著書にこのような一節がある。
「我々の周りはプロダクトであふれています。身近なものでは、社内で使うシステムや各種ツールなどもそうです。社内プロダクトであっても、顧客である社員を理解し、適切に開発され、継続的に改善されることで、企業全体の生産性や社員のモチベーションに大きく影響するのです。」
ソフトウェアを使って、業務を効率化して従業員の負担を軽減することも、新しいビジネスを立ち上げて新たな収益源を生みだすことも「プロダクト」を作ることだ。もちろん上述した「工業製品」も「ソフトウェア・パッケージ」もプロダクトである。
これらプロダクトを生みだす起点は、「何をしたいか、何を解決したいか」の問いである。これを明確に言語化し、ぶらすことなく貫いてこそ、プロダクトは成功する。プロダクトを実現する過程で、その実現の手段に迷ったときは、この起点に立ち戻り、この問いを実現する上での最善は何かを考えて選択することが大切であると説いている。
冒頭でも述べたように、「ソフトウェアこそ価値の源泉」である。つまり、「プロダクトの価値はソフトウェアで実装され、それを実現する手段としてハードウェアは位置付けられる」とすれば、プロダクトにおける、ソフトウェアの果たす役割は大きい。
少し言い過ぎかも知れないが、「ビジネスや社会はプロダクトの集合体」という捉え方もできるだろう。そんなプロダクトは「ソフトウェアが支配する」とも言える。「ソフトウェアファースト」とは、そんな価値観を表す言葉なのかも知れない。
昨今、ユーザー企業による情報システム(ソフトウェア)の「内製化」が拡大している。及川さんはこれを「手の内化」と述べているが、日本もやっとソフトウェアの大切さに気づき、コアコンピタンスとして自らに取り込もうとしている。
2019年に彼が上梓した「ソフトウェア・ファースト(初版)」は、そんな世の中の動きを呼応して、「ソフトウェア・ファースト」という言葉が広まるきっかけとなった。いまや、この言葉は日常的なビジネス用語となっている。
本書は、その「リフレッシュ(refresh)」版である。refreshとは、「再び新しくする」、「古くなったものを再生すること」である。いまの時代に合わせて、あるいは、彼のこの間の経験の蓄積が、旧版の内容をrefreshしている。
この言葉には、もうひとつの含意がある。「元気を回復すること。気分をさわやかにすること。」まさにいまの時代にふさわしい。これこそが、本書の「何をしたいか、何を解決したいか」であり、彼の描くプロダクトの体現なのだろう。
6月22日・販売開始!【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。