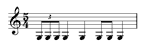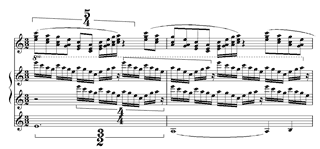惑星の前衛的オスティナート
先日N響アワーで、ホルストの「惑星」をやっていた。この作品は、古くは冨田勲のシンセサイザー、最近では、平原綾香の「Jupiter」やビートたけしのTVタックルのBGMなどで、クラシックファンならずとも認知が高い。人気のある分かりやすい旋律は、威風堂々のエルガー同様、極めて英国的なもので、宇宙空間というより地上的なものだ。とはいえ、この作品によって宇宙を想像できるのは事実なので、その辺を少し紐解いてみようと思う。
「惑星」の中でも、「木星」に代表されるようなわかりやすい旋律はさておき、全編で多用される共通した手法は「オスティナート」だ。オスティナートは、同じ音形を執拗に繰り返す手法で、「惑星」では、すでに冒頭の「火星」の5拍子の音形に表れている。もっとも、ここでの使い方は、伴奏音形としてのオスティナートであり、ロックのビートと同様、必須ではあるものの、それだけで音楽を構成しているわけではない。
しかし、曲が後半に行くに従って、オスティナートの使い方が段々前衛的になってくる。例えば、「水星」などは、古典的な耳では軽快なスケルツォと聴くこともできるが、ほとんどライヒの反復音楽のような箇所もある。そして、太陽からはるか14億キロ以上離れた「土星」では、確固たる旋律線よりもオスティナートが醸しだす空間音が音楽そのものになっている。しかも、6拍子の中に、5拍子、4拍子など、さまざまな周期のオスティナートが、開始点をずらして同居している。
ひとつひとつの音形を切り出してみると、大したことはない。しかし、これが重なり合うと、無限感を感じる から不思議だ。恐らくこれを究極の状態にしたのが、最後の「海王星」で、スコアには、クラッシック音楽ながら「Fade Out」の指示がある。もはや「ブラボー隊」の入り込む余地はない。
ただ、冷静に考えてみると、我々の想像しうる宇宙観を、20世紀初頭のホルストが持っていたかというとかなり違っていたはずだ。彼の時代は、天体観測技術の発達により、新しい惑星が発見されてきていた(海王星の発見が1846年、冥王星の発見が1930年)ものの、それを探査線からの映像で直接見たり、CGによって作られた宇宙をビジュアルに体験できる我々の時代とはまったく違う宇宙感があったはずである。だとすれば、なぜ、今我々がホルストを聴いて、現在の宇宙感による惑星イメージを膨らませることができるのだろうか。
その理由は、まず、上で述べたようホルストの手法が、宇宙を描写する定番パターンのひとつとなったからだ。ホルスト的なオスティナートによる音楽が、宇宙空間を描く映画やビデオ画像に重ねられ、逆に宇宙のイメージとして定着しているのだ。エイリアンなどの音楽を聴いてみてほしい(スターウォーズは厳密には時代劇の分類だと思うので別)。つまり、ホルストが現代的な宇宙感を描画したのではなく、ホルストの音楽が現代人の宇宙感に重ねられ、学習させられているということなのだろう。
もうひとつには、この音楽が極めて表題的でありながら、決して宇宙そのものを描画していない点にある。宇宙をテーマにしていながら、現実には神話やそれの投影である現実世界、つまりは「人」を描画しているのだ。そのため、CGや知識で理解している惑星のすがたを、我々自身が擬人化して投影する媒体としてこの音楽を聴き、想像力を膨らませることができるのだと思う。
ちなみに、惑星には、その後発見された「冥王星」を別の作曲家が書き加えた新バージョンもある。しかし、新たに明らかになった知識がじゃまをするのか、どうも描画が直接的すぎて、ホルストのような想像力の幅に乏しい感じがする。