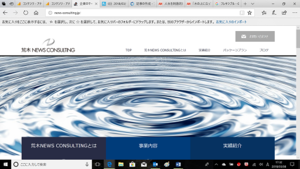4頭のヒグマに追い込まれた絶望的な登山
唐突だが、クマに襲われたことがあるだろうか?
ボクはある。
正確に言えば、襲われたというより「ヒグマの戦略にまんまとハメられた」という方が近いかもしれない。ボクを含めた見ず知らずの11人の登山者は、知床の山奥で4頭のヒグマに囲まれ、絶体絶命の状況まで追い込まれた。ヒグマたちは、あたかも人間狩りを楽しむようにボクらをもてあそんだ。
「そんな馬鹿な話あるか」と思うかもしれないが、その場にいた11人はきっと今でも「見事にヒグマに騙された」と思っているに違いない
その絶望的な体験は、ちょうど3年前のお盆だった。
ボクは北海道ツーリングの一人旅に出た。バイクにテントを積み、2週間かけて北海道のキャンプ地をめぐりながら「登れるだけの百名山に登ろう」という旅だった。
東京を出てバイクで北海道に上陸すると、まずは道内の最高峰である「旭岳」に登り、次に「利尻山」へ向かった。〝日本最北端の百名山〟とも言われるように、最果ての離島「利尻島」にそびえる山で、登山はもちろん島に渡るだけでも十分に刺激的な場所だった。
そして、3番目の山に選んだのが知床にある「羅臼岳」だった。
知床のキャンプ地に前泊し、翌朝6時から登りはじめた。山は何があるか分からないので「早く登って、早く下りる」のが鉄則で、昼過ぎには下山する予定だった。
知床の街には観光客が溢れていたが、さすがに登山までしようという者は少ないらしく、登山開始から1時間が過ぎても誰にも会わなかった。登山道の両脇からせり出す茂みのせいで視界はあまりきかず、やぶのなかを進んでいるようなものだった。
水を飲むため立ち止まるたびに、クマ除けとしてリュックにぶら下げた鈴の音もピタリと止む。すると、何の音もしない無音の世界が広がる。この山に登山客はいないのか――。次第に恐怖が募ってきた。
ようやく前方に微かながら鈴の音が聞こえたのは、登山を開始してから1時間半が過ぎた頃だった。登るにつれて鈴の音は徐々に近づき、ついにあと10メートルというところまで迫った。ただ、やぶが深すぎて前を歩く登山者の姿はまったく見えない。
登山道は非常に狭い一本道である。そろそろ見えない登山者に声を駆けて抜こうか――。そう思ったときだった。
「ガルルルルルル...」
聞いたことのない野太い唸り声が前方から聞こえてきた。
「............」
ボクはとっさに歩みを止め、反射的に息を止めた。何かいる――。同じく、前方にいる登山者の鈴の音もピタリと止んだ。そして次の瞬間、前方の茂みがワッサーと大きく揺れると同時に「ガルルルルルル」という唸り声が一気に迫ってきた。
あ......、前の登山者が襲われている......。
格闘しているらしい激しい音が聞こえてきた。唸り声の調子はさらに激しくなり、それは山中を響き、相当に怒り狂っているようだった。
――数秒後。
悲鳴のような短い声を残して、何かが深い崖下まで滑落していく音が聞こえ、やがて遥か下からドスンという鈍い音が響いた。20メートルはあろうかという崖だ。辺りを土煙が舞っていた。
すぐ目の前で起きた惨劇。しかし、すべてはやぶの向こう。何か重大なことが起きているはずなのに音しか聞こえず、それが余計に恐怖をあおった。
ボクは1分ほど息を止めていた。逃げようだなんて思いつきもしなかった。本能が動くなと警告しており、小指1本すら動かすことができなかった。「何か」が茂みの奥からこちらを狙っている気配がありありとした。
辺りは不思議なほどの静寂に包まれている。
俺もヤラれるのか――。
と、ふいに前方のやぶがワサワサと揺れ、草の間から何かが勢いよく転がってきた。
「...ったまげたぁ。ほれ、あんちゃん、今のうちさ、早く逃げっぺ!」
現れたのは小柄な老人だった。髪の毛は逆立ち、目は真っ赤に血走り、口の両脇から白い泡が漏れていた。事情も飲み込めないまま200メートルほど登山道を引き返し、多少視界が明るいところでようやく老人はリュックを降ろし、その場にしゃがみ込んだ。
「おっかねかったぁ。一歩間違ってたら、オラ、今頃あの崖の下でペチャンコになってたっぺ......」
老人いわく、茂みから突然ヒグマが襲ってきたという。やはり「何か」はヒグマだった。かろうじてトレッキングポールで身を防ぎ、ヒグマの頭を叩いて追い払ったという。彼の唇は紫色に変色していた。
ヒグマはまだその辺に潜んでいるかもしれずヘタに動かない方がいいということで、1時間ほどその場で待機した。落ち着きを取り戻した老人は呑気にタバコを吸いながら、時おり爆竹に火をつけてはやぶのなかに放り込み、ヒグマがいないかどうか耳をそばだてた。
しばらくすると男性登山者が1人やってきた。見るからに真面目そうな40代サラリーマンで「係長」という雰囲気だった。彼に事情を説明すると「後ろからもう1人来てます」と言うので、その登山者を待つことにしたのだが、現れた男を見てボクは愕然とした。
「おお、Ninjaのあんさんやん!」
男は親し気に寄ってきた。「Ninja」とはボクのバイクのことだ。
「ほぇ? 知り合いだっぺか?」
老人が尋ねるのでボクは首を横に振ったが、男はウンウンと頷いた。
昨晩、たまたま知床のキャンプ地で出会い、ちょっと話しただけだった。男もボクと同じくライダーだったが「旅行者」というにはかなり趣きが異なる。
男のバイクの荷台には家財道具全てが積まれているのではないかというほどの荷物が詰まれ、また、30代半ばとは思えぬ年季の入ったアゴ鬚が一般人と異なる雰囲気を醸していた。時代遅れのヒッピーか、あてのない放浪者か。どういうわけか「レゲエマン」というあだ名が自然と思い浮かんだ。
ボクが「明日、羅臼岳に登る」と言うと「ほな、ワイも登ったろかなぁ」と言ったのは、冗談ではなかったのだ。
当然、レゲエマンは思いつきの登山だから小さなナップサックしか背負っておらず、半袖に短パンで、足元は靴底のすり減ったスニーカーというふざけた格好だった。ボクだけでなく老人も、係長みたいな中年男性も呆れていたが、レゲエマンはちっとも意に介さなかった。
「ここで出会ったのも何かの縁や。せっかくやし、この4人でパーティー組んで登ろうやないか。ヒグマに襲われたおっちゃん、アンタ、今から隊長や」
出だしから奇妙な登山となった。
1時間ほど登ると急に視界が開け、目の前には巨大な雪渓が現れた。さすが知床、真夏でも雪がしっかり残っているのだ。
長さ300メートルほどの雪渓は登りづらいが、しかし、これが唯一の登山道。ここを進むしかない。不思議なことに、ツルツルのスニーカーのレゲエマンは猿のように身軽に登っていく。
雪渓を登り終えると「羅臼平」という広大な平地が広がっており、3人組の登山者が松林の奥を指さし何やら相談していた。隊長が先に行って話を聞きに向かい、やがて苦笑しながら帰ってきた。
「またヒグマだっぺ......。デカいのがウロついて離れないらしい。1日に2頭も会うなんて、今日は何だかヘンだっぺ」
目を凝らすと、確かに200メートルほど先の松林のなかに黒い物体が見える。初めて見る生のヒグマだった。遠すぎるためさほど恐怖は感じないが、それとは対照的に今しがた隊長が襲われた際の獰猛な唸り声が、頭のなかをしつこくこだましていた。
人間の存在に気づいているのか、気づいていないのか、ヒグマはなかなか去ろうとしない。
結局、1時間ほどその場で待機し、ヒグマの姿が消えるのを待ってから登山を再開した。隊長の「襲撃事件」の話を聞いた3人組も怖くなったらしく、我々4人の即席パーティーの後ろを何となくついてきて、7人で山頂を目指すことになった。
頂上は絶景だった。
「もともと登山道はヒグマの通り道さ。オラたち人間が、そこを通ってるだけだっぺ」
隊長はみなに山の話を語って聞かせてくれた。彼はリタイアしてから北海道全土の山を歩いており、今回の羅臼岳だけでも5度目といい、ヒグマの生態にも詳しかった。なかでも驚いたのは、山によってヒグマの性格が異なるという話だった。
「斜里岳のヒグマはやんちゃだぁ、オラ、あそこは苦手だっぺ」
斜里岳はここから遠くない。では、大人しいはずの羅臼岳のヒグマはなぜいきなり襲ってきたのだろうか。
「クマさ、朝ゴハンの最中だったんだっぺ。その脇をオラがうっかり通ったから、怒ったんでないかい?」
不思議な方言は、登山をするため北海道に移住したからだそうで、元はどこの生まれかは言わなかった。しかし、何はともあれ下山に向けて心強い味方だった。
が、しかし。
不幸の始まりはこれからだった。
7人で岩場だらけの山頂を降り、まずは平らな松林が広がる羅臼平まで戻った。先ほどウロついていたヒグマの姿はなく、みな安堵して巨大な雪渓まで進んだ。頂上から見下ろすその光景は、さながらスキーのジャンプ台のてっぺんにいるようだった。
さっそく降りようとしたところ、ふいに無口な係長が口を開いた。
「......ちょっと待ってください。あの黒い岩みたいなの、あれってヒグマじゃないですか?」
確かに何かが動いている。間違いない、ヒグマだ。白い雪の上にいるからよく目立つ。
「やっぱ今日の羅臼岳は何かおかしい。ヒグマたちが騒いでるっぺ......」
隊長が首をかしげた。ベテランの彼にとっても初めての事態らしい。ただ、雪渓=登山道。ここを通らなければ下山できない。ヒグマは何をするでもなく座ったり立ったりを繰り返すばかりでボクら7人は下りるに下りられず、3度目の待機をする羽目になった。
30分ほどして、若い女性の声が上の方から聞こえてきた。山頂を降りるときにすれ違った20代前半の山ガール2人組だった。雪渓にヒグマがいて下山できないことを伝えると、山ガールは顔を見合わせ歓声をあげた。
「うそ? クマさん? 超見たい!」
「姉ちゃんたち、アホちゃうか」
レゲエマンが突っ込みを入れたが、彼女たちは彼のヒッピーじみた風貌をチラッと見てすぐに無視を決め込んだ。レゲエマンは、ヒグマ以下の存在らしい。
彼女たちは遥か下方にいるヒグマを眺めつつ、おかしなことを口にした。
「今下りてきた松林のなかにも1頭いましたよ。頭だけ見えたけどすぐ見えなくなっちゃって、残念ネって話してたところなんです」
おそらく行きに遭遇したヤツだ。どの辺りで目撃したか尋ねると、ここから100メートルもないと呑気に答え、しかも雪渓の方へ向かっていたと言う。
冗談じゃない――。ボクと隊長は同時に茂みを振り返った。今朝の襲撃が蘇ったのだ。突然あの茂みから唸り声が聞こえてもおかしくない。
「とりあえず下りられる辺りまで下りるっぺ」
見える敵より「見えない敵」の方が危険なのだろう。山ガール2人が加わり9人となった即席パーティーは雪渓を100メートルほど下った。「うわ、超滑る!」「楽しいかも!」など山ガールの2人は危機感のかけらもなく、ぽっちゃりした女性の方は事実、よく尻餅をついては大笑いした。雪渓の途中に大きな岩があり、我々はそこに隠れることにした。
ヒグマは依然その場を動かない。かなり近づいたが、まだ距離は200メートルほどある。ただ、それはあってないに等しい距離。じっと岩陰から見守っていると、さすがにヒグマも我々の存在に気が付いたのか、唐突にこちらの方に顔を向けた。
と、次の瞬間、ヒグマは頭を大きく下に揺らしたと思ったらむくりと起こし、いきなりこちらに向かって駆けだしてきた。
......え?
ヒグマのきまぐれな行動だったのかもしれない。あるいは、人間に対する威嚇行動にも思えた。だとするなら、その効果は十分すぎるほどあった。ヒグマは4歩、5歩駆けただけで十数メートルも進み、何よりおそろしく俊敏な姿に度肝を抜かれた。
予想外の事態に我々は一斉に逃げ出そうとしたものの、足元が滑ってまともに歩くこともできず完全なパニックに陥った。今襲われたらひとたまりもない。全員アウトだろう。ぽっちゃり女性はまたもや転んだが、さすがに涙目になっていた。
ヒグマは再びその場に座り込んでしまった。何をしているのかさっぱりわからないが、人間を意識しているのはもはや明らかだった。雪渓のうえで黒いヒグマはよく目立った。反対にいえば、ヒグマの目からも人間はよく目立つ。もしや、岩陰に隠れている人間の数を確認するための作戦だったのかもしれない。
さらに岩陰で待つこと30分。
ふと、ヒグマが首をもたげた。また威嚇する気だろうか。だが、違った。ヒグマのすぐそばの茂みがワサワサと揺れ始めた。まさか。とは思ったが、そのまさかだった。
新たなヒグマが雪渓に姿を現した。
茶色の立派なヒグマだった。先にいた黒クマは呼応するように立ち上がると、茶グマはそれに構わずゆっくり近づていき、やがて2頭は取っ組み合いを始めた。山ガールの片方が小さな悲鳴を上げた。
2頭はケンカしているのかと思ったがそうではなく、どうやら兄弟のようで、相撲を楽しむかのようにじゃれ合っている。何だかおとぎ話を見ているようだった。しばらくすると2頭は仲良く雪渓に座り込んでしまい、登山道は2頭によって完全に塞がれてしまった。
「ヒグマの相撲だなんて、オラ、こんなの見たことねえっぺ......」
隊長は絶望的なため息をついた。
「おいおい、これってクマにハメられたんとちゃうか?」
レゲエマンは険しい眼差しで雪渓の上を見上げた。確かに、あの茂みのなかには1頭が迫ってきている。無事に雪渓を抜けたとしても、その先には隊長を襲った1頭が潜んでいる。そして目の前には、しっかり行く手を塞いでいる2頭――。人間にとって圧倒的な不利な雪渓。そのど真ん中に、見事におびき出されたように思えなくもない。
ボクは空を見上げた。陽射しがやや黄色がかってきており、いつのまにか夕暮れが近づいていた。一瞬、ビバークが脳裏をよぎったものの、ここはヒグマの王国。4頭以外にも無数のヒグマが潜んでおり、知床の夏は寒い。
レゲエマンの言葉にみなが黙り始めたとき、雪渓の上から何かが勢いよく滑り降りてきた。一瞬、ヒグマかと思ったが、それは2人組の男性だった。どうやら別の登山道から来たらしいのだが、奇妙ないでたちが目を引いた。
「チワっす! みんなで何してんスか?」
大学生だろうか、いかにもチャラそうな青年は半袖、短パン、スニーカーで、まるで海に遊びに行くような恰好をしていた。もう一方の男がもっと怪しい。年齢は30代半ばくらいだろうか。グレーの長袖のワイシャツに黒いスラックス。なぜか手には闇金が愛用しそうな黒皮のセカンドバック――。どう見てもVシネに出てきそうなチンピラ風情で、頬のこけた精悍な顔つきがまたそれっぽい雰囲気をかもしていた。
「あいつら、山をナメとんのとちゃうか?」
レゲエマンが立派なアゴ髭を撫でながら呟いたが、彼もまた短パンにスニーカーという思いつきの登山者だ。「お前が言うな」と言いそうになったが、よくよく考えるとまったくの他人であり、そもそもレゲエマンも何者なのかサッパリだった。
何にせよ、怪しげな2人組の登場により我々の雰囲気は一変した。隊長が事情を説明すると、チャラい青年は「マジで? 2頭もいんじゃんかよ!」と叫ぶなり、しゃがんでソフトボールほどの雪玉をつくった。え? まさか――。誰もがそう思ったが、止めるも間もなくチャラ男はヒグマ目がけて雪玉を投げた。
こいつ、頭おかしいのか――。
チャラ男の行動はもはや予測不能だった。もう1つ雪玉をつくると、それを手に独りで雪渓を下りはじめた。横顔が笑っていた。どうみても直接ヒグマに投げつけるつもりだ。慌てて相棒のVシネが頭を下げつつ後を追った。
「すいませんね、コイツはちょっと常識知らずなもんで」
何なんだ、この2人組。俺らを巻き添えに自殺でもする気か。勝手にすればいい。ところが予想外にも隊長が彼らの後をついていった。
「オラたちも行くっぺ」
隊長は黄色くなりつつある空を見上げた。確かにこれがラストチャンスかもしれない。
「あの2人、いっそのことヒグマに喰われたら面白いですね。その隙に我々逃げれますよ」
係長が真顔で言うと、レゲエマンは無言でうなずいた。じつはボクも同じことを考えていた。
2人増えて11人となった即席パーティーは一気に雪渓を降り、ヒグマまで50メートルの茂みに身を隠した。ぐっとヒグマの姿が大きくなった。もはや逃げ場はどこにもなかった。
「......もう、どうしようもねぇ。オラ、ヒグマと登山道の間に立って見張るから、みんなはヒグマの前を順に渡るッぺ。慌てるでねぇぞ」
隊長はおもむろにリュックのなかを探し始めた。出てきたのは、刃渡り20センチはあろうかというランボーナイフだった。
「オラが合図したら、みんな来い」
隊長はずんずんとヒグマに近づいて行った。すごい度胸で、むしろ見ているこちらの方が息苦しくなってきた。山ガールのぽっちゃり女性もリュックをまさぐりだしたが、出てきたモノを見てため息が漏れた。クマ除けスプレーだった。あの巨大な2頭を前に、それは殺虫剤ほどにしか見えない。
やがて隊長が手招きで合図した。もう彼を信じるほかない。
我々は茂みを出て、ついにヒグマの元へと向かった。
2頭のヒグマの目の前を順番に抜ける――。
この不思議なミッションにおいて最も重要なのは位置取りだった。まず先頭は避けなければならない。真っ先に襲われる可能性が高い。一方、最後尾も不安だった。ヒグマに追いかけられたら最初にヤラれる。登山道は追い抜きできないほど狭く、しかも雪で滑る。
やはり、列の中ほどがベストだろう――。
隊長の元へと向かいながら、ボクはさりげなく靴紐を結んだりしながら真ん中を狙った。ただ、みな同じことを考えていた。立ち止まって水を飲んだりタオルで汗を拭いたり、どうにか真ん中をキープしようと静かな駆け引きが始まった。みな、赤の他人なのだ。
「あんさん、クマ子の後ろはアカンで。あいつが尻餅ついたら前には逃げれへん」
レゲエマンはしゃがみ込み、靴紐を直すフリをしながらボクの耳元に囁いた。クマ子とはよく思いついたな――。この場面で何とも絶妙なネーミングに、ちょっと笑ってしまった。彼に忠告されるまでもなく、ボクも、そしておそらく全員がクマ子の前を狙っていた。
幸い、命知らずのチャラ男とVシネが先頭となり、ボクとレゲエマンは中ほどをゲットし、みなから警戒されたクマ子は最後尾となった。
そして、そのときがやってきた。
2頭のヒグマは登山道に背を向け、茂みのなかで何かをむさぼっている。とはいえ、ヒグマまで10メートルもない。何かの拍子にヒグマが振り向けば、2秒もかからずヒグマの巨大な手が襲ってくるだろう。
気のせいか獣の臭いが辺りを漂う。ここだけ空気がピンと張りつめている。そして、不思議なほど静かだった。ここは人間の世界ではなく、完全にヒグマの世界だった。
我々は一列に並んで隊長の合図を待った。気づけば、全員が鈴をリュックのなかにしまっていた。ヘタに音を出して目立つのを嫌ったのだ。
最初にチャラ男が行った。彼は平然とした様子でヒグマの前まで歩くと、ヒグマに向かって大きく手を振って自分をアピールした。どこまでもアホというか、迷惑極まりない。隊長が早く行けと目で何度も促し、ようやくその場を去った。
次がVシネだった。なぜか彼は、ヒグマの前でもガニ股で肩を揺らしながら悠然と歩く「チンピラスタイル」を貫いた。そのクソ度胸はヒグマに見せたいのか、我々に披露しているのかよく分からないが、時間がかかってはた迷惑でしかない。
そしてボクの番がきた。あんな無茶な歩き方の2人が無事に過ぎたのだから、自分も大丈夫だろうと思った。
ボクは空を見上げた。大きな鳥が飛んでいる。
息を大きく吸い込んでから歩き始めた。
近づくにつれてヒグマの世界が濃くなっていく。吐き気がこみあげてくる。先頭の2人はやはり頭がおかしいのだろう。
そして、ついにヒグマの目の前にきた。
今思えば、ボクは静かに興奮していたのだろう。ヘタすれば一瞬で殺される――。そんな恐怖を覚えつつ、その一方で神々しいヒグマの姿に引き込まれてしまった。立派な姿だった。綺麗だった。アイヌの世界で「神」と崇められるのが分かる気がした。
そのときだった。背を向けて何かをむさぼっていた茶グマの動きが急に止まった。それからおもむろに頭を起こすと、ゆっくりボクの方を振り向いた。
え? なんで俺?
完全にヒグマと目が合ってしまった。黄色くて、真ん丸で、ビー玉みたいな目だった。それがじっとボクを凝視している。怒っているのか、人間を不思議がっているのか、それともただ関心を持っただけなのか、感情がまったく読めない。恐ろしいほど感情がない。
異変に気づいた隊長がゆっくり背後を振り向いた。それが、さらに茶グマの何かを刺激したらしい。耳を立てた茶グマはゆっくりと上半身を起こした。それだけで2メートル近い。立ち上がる前兆であることは誰の目にも明らかだった。
ボクの背後、列を待つなかから大きな悲鳴が聞こえた。
――その後のことはよく覚えていない。
気づくと猛スピードで茂みのなかを下山していた。前には、見張りをしていたはずの隊長の背中があり、後ろには血走った目のレゲエマン、その後ろには係長が続いており、係長はなぜか半笑いを浮かべていた。結局、初期メンバーの4人に戻っていた。
とりあえず助かったらしい。ただ、この茂みのなかにも隊長を襲ったヒグマが潜んでいる。4人は無言のままひたすら山を下り、ようやく足を止めたのは30分ほどしてからだった。そこだけ周囲の木々が少なく視界がきき、上にはかろうじて空が見えた。
「他の人たちは?」
ボクが尋ねると「みな無事や」と、レゲエマンが短く答えた。
「あのチンピラみたいな男、何だったぺなぁ?」
「......さあ」
しばらくして最初に会った3人組が合流した。それから7人で2時間ほどかけて下山した。麓にあるロッジの屋根が見えてくるとだれかれとなく子供のように走り出し、ロッジに到着した途端、たまらず全員が大笑いを始めた。
一斉に緊張の糸が途切れたのだ。みなワケもなくずっと笑っていた。4頭のヒグマに囲まれたり、チンピラが現れたり、ヒグマが相撲を取ったり、命をかけた場所取りに執念を燃やしたり――。いざ普通の世界に帰ってきたら、それは嘘みたいな1日だった。
「こんなおかしな登山、誰も信じへんやろな......」
しみじみとレゲエマンが呟いた。結局、彼が何者なのか知らないままだったが、そんなことはどうでもよかった。一生出会うことはないだろうが、素敵な仲間に出会えた気分だった。
「もうオラ、ヒグマはこりごりだぁ。今日で登山は引退すっぺ......」
力なく笑う隊長に、みんなが微笑んだ。
(荒木NEWS CONSULTING 荒木亨二)
マーケティングを立て直す専門のコンサルティングです。詳しくは下記Webサイトをご覧ください。