進化が激しすぎる! ~利用者泣かせの生成AI
最近毎回のように書いていますが、生成AIの進化の速度は異常に速く、今書いていることが次の瞬間には嘘になっている、ということが頻繁に起きます。最近の講演では生成AIの活用についてお話しすることが多いのですが、その際もかなり気を使います。実例を挙げて説明する場合には、主要な機能については直前にチェックするのですが、それでも話し終えた時点で変わっていないという保証はありません。
 そもそも現在の生成AIは過去のデータの学習から確率的に文章を生成するという仕組みになっているため、同じプロンプトに対する応答が微妙に変化するという問題があります。これはハルシネーションではなく、生成AIの仕組みからくる、避けられない問題です。
そもそも現在の生成AIは過去のデータの学習から確率的に文章を生成するという仕組みになっているため、同じプロンプトに対する応答が微妙に変化するという問題があります。これはハルシネーションではなく、生成AIの仕組みからくる、避けられない問題です。
さらにこれに、生成AIの開発速度が速いために時々刻々とアップデートが行われ、そのために応答が変わってくるという問題が加わるのです。
これは、性能を高めるために何を重視して何を取捨選択するかという開発方針の反映でもあり、なかなか難しいところです。これまでは、皆同じ方向を見て開発を進めてきたと思うのですが、ここへ来て生成AI間の開発方針の違いによる特徴が出てきて、何を重視し何を切り捨てるかというベンダー側の考え方がサービスに色濃く反映されるようになったということでしょう。さらに、生成AIを日々の生活や日常業務の中で活用する機会が増えていることから、過去との微妙な違いが、その機能を愛用していたユーザーにとって大きな出来事のように感じられる、ということなのかも知れません。
軽視できない「ダウングレード」問題
これは講演者泣かせだけではなく、本当に大変なのはエンドユーザーでしょう。ただでさえアップデートに追いついていくのが大変な上に、一般的なサービスではなかなか見ない「ダウングレード」が起きることがあるからです。ダウングレードとは「これまでできていたことができなくなる」ことで、先週書いたような「GPT-5問題」には、どうもこの問題が含まれているようです。
GPT-5では、それまでいくつもあったAIモデルが一本化されました。これは「モデルが多すぎてどれを使ったら良いかわからない」というユーザーの声に応えたものです。GPT-5では「オートルーター」によって最適なモデルが選択されると言うことですが、どのモデルを選ぶかはOpenAI側が決めるわけです。そうすると、ユーザーがそれまで使っていたモデルが選択されない場合が当然出てきます。そうすると以前のような応答が得られなくなり、それがユーザーに「応答品質が落ちた」と思わせる原因となっているというのです。
「これまでできなかったことがいつの間にかできるようになっていた」のであればまだ良いのですが、「これまでできていたことがいつの間にかできなくなっていた」というのは、本当に困ります。それが先週書いたような「モノの言い方」に関することならまだしも、うまく動くと思ってそれを前提に業務を作り込んでしまっていたりすると、最悪担当者の責任問題にもなりかねません。ユーザー側も気を抜けない、大変な時代になってしまったものです。
【募集開始】ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日〜)
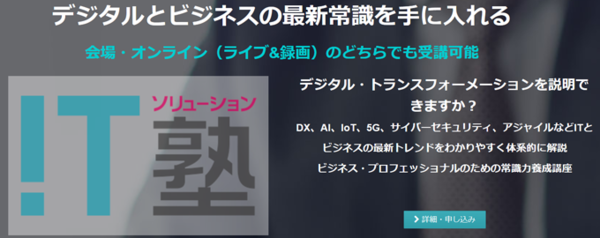 次期ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日 開講)の参加者募集を開始しました。
次期ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日 開講)の参加者募集を開始しました。
ITベンダーにお勤めの方、ユーザー企業でDXやAIに取り組んでいる方向けに、毎週一回、さまざまなトピックを取り上げ、最新のITトレンドについて知識を深めていただきます。また、現在注目されているさまざまな技術が相互にどのように連携しているのか、歴史的な視点を交えて解説することで、技術の本質を理解していただきます。知識を真に内面化するためには、表層的な概念では無く、本質を理解することが重要です。
たとえば、AIサービスを賢く使いこなすためには、AIの仕組みやこれまでの進化の過程を理解することが重要です。そしてそれをビジネスに適用していくためには、AIそのものももちろん重要ですが、Web3やIoT、アジャイル開発/DevOpsといった分野にAIがどのような影響を与えていくのかを、幅広い視点から捉える必要があります。ビジネス環境全体を俯瞰し、各々のテクノロジーがどのように関連し、連携しているかを捉えることで、トレンドを掴むことができるのです。
ITソリューション塾では、最新技術の中身を紹介するだけで無く、他の技術との関わりや歴史的経緯を理解していただくことで、より広い視野の元で最新のトレンドを考えていただけるような講義を目指しています。
- 日程 :初回2025年10月8日(水)~最終回12月17日(水) 毎回18:30~20:30
- 回数 :全10回+特別補講
- 定員 :120名
- 会場 :オンライン(ライブと録画)
- 料金 :¥90,000- (税込み¥99,000) 全期間の参加費と資料・教材を含む
詳細なスケジュールは、こちらです。