GPT-5と同時に発表されたgpt-ossの「オープンウェイト」モデルとは何か?オープンソースとの違いは?
8月7日に鳴り物入りで発表され、その後「肩透かし」「改悪」など、大きな反響を呼んだGPT-5の影に隠れてあまり注目されていませんが、OpenAIは8月5日にgpt-ossというオープンウェイトモデルも発表しています。そして一部では、こちらのほうがGPT-5よりも大きな意味を持つのでは、とも言われているのです。
その意味については別途まとめてみたいと思いますが、今日はその前段階として、用語の問題について考えて見たいと思います。というのも、この件については以下の様にいろいろな記事があるのですが、
gpt-ossのことをGPTシリーズの「オープンソース版」と紹介している記事が多いのです。これは、gpt-ossという名前から来る誤解だと思うのですが、OpenAIのサイトを見てみると、
サブタイトルに「オープンウェイトリーズニングモデルの限界を押し広げる gpt-oss-120b と gpt-oss-20b」とあり、本文にも
低コストで強力な実世界パフォーマンスを実現する2つの最先端のオープンウェイト言語モデルの gpt-oss-120b と gpt-oss-20b をリリースします。
と書いてあります。どうやら、OpenAIの公式見解としては「オープンウェイト」であり、「オープンソース」では無いようです。
 「そんなもの、似たようなものだろうが」と思うかもしれませんが、LLMにおいてオープンソースとオープンウェイトでは明確な違いがあります。以下、ChatGPTの回答です。
「そんなもの、似たようなものだろうが」と思うかもしれませんが、LLMにおいてオープンソースとオープンウェイトでは明確な違いがあります。以下、ChatGPTの回答です。
オープンソース(Open-source)は、ソースコード全体を公開し、誰でも閲覧・改変・再配布が可能です。AIモデルの場合は、モデルの学習コード、学習データの取得方法や前処理スクリプト、推論コード、トレーニング済みモデルの重み(パラメータ)などが全て公開されます。
オープンウェイト(Open-weight)は、レーニング済みAIモデルの**重み(weights、パラメータ)**と推論に必要な最小限のコードのみ公開します。トレーニングデータセットや学習時のコードや手順、ハイパーパラメータの詳細は公開されません。
オープンソースの利点としては、透明性が高く、再現性のある研究や完全なカスタマイズが可能である点で、オープンウェイトの利点は、高度なモデルを研究者や企業がローカル環境で利用・微調整できることだそうです。「研究や教育にはオープンソース、実用・商用にはオープンウェイト」ということですね。
つまりgpt-ossは、企業が社内にダウンロードして自社環境で自由に使うことができるため、ユーザーが入力したデータが外部に漏れる心配が無い、ということになります。また、パラメータの微調整もある程度可能になることで、自社向けにカスタマイズしたり精度を高めたりできる可能性もあります。
技術やノウハウがまるごと公開されてしまうオープンソースではなく、オープンウェイトという形態をとったのは、OpenAIが自社のメリットと利用企業のメリットを最大化するために選んだ結果と言えるでしょう。
【募集開始】ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日〜)
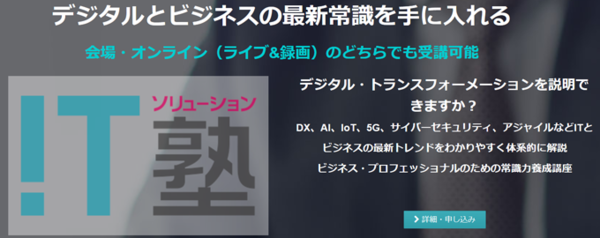 次期ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日 開講)の募集を開始しました。
次期ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日 開講)の募集を開始しました。
ITベンダーにお勤めの方、ユーザー企業でDXやAIに取り組んでいる方向けに、毎週一回、さまざまなトピックを取り上げ、最新のITトレンドについて知識を深めていただきます。また、現在注目されているさまざまな技術が相互にどのように連携しているのか、歴史的な視点を交えて解説することで、技術の本質を理解していただきます。知識を真に内面化するためには、表層的な概念では無く、本質を理解することが重要です。
たとえば、AIサービスを賢く使いこなすためには、AIの仕組みやこれまでの進化の過程を理解することが重要です。そしてそれをビジネスに適用していくためには、AIそのものももちろん重要ですが、Web3やIoT、アジャイル開発/DevOpsといった分野にAIがどのような影響を与えていくのかを、幅広い視点から捉える必要があります。ビジネス環境全体を俯瞰し、各々のテクノロジーがどのように関連し、連携しているかを捉えることで、トレンドを掴むことができるのです。
ITソリューション塾では、最新技術の中身を紹介するだけで無く、他の技術との関わりや歴史的経緯を理解していただくことで、より広い視野の元で最新のトレンドを考えていただけるような講義を目指しています。
- 日程 :初回2025年10月8日(水)~最終回12月17日(水) 毎回18:30~20:30
- 回数 :全10回+特別補講
- 定員 :120名
- 会場 :オンライン(Zoomによるライブ配信と録画)
- 料金 :¥90,000- (税込み¥99,000) 全期間の参加費と資料・教材を含む
詳細なスケジュールは、こちらです。