OpenAIがgpt-ossを発表した背景にある「不都合な真実」とは
OpenAIが発表したgpt-ossに関連して、先週はオープンソースとオープンウェイトの違いについて書きましたが、今回はOpenAIがオープンウェイトモデルを採用した背景について考えてみたいと思います。
先週の記事でも挙げましたが、gpt-ossについては肯定的な意見が目に付きます。
このように、ユーザー側にはさまざまなメリットがあるオープンモデルですが、どうやらそこには、ベンダー側の事情もありそうです。
 オープンウェイトモデルは、オープンソースほどでは無いにせよ、自社のノウハウや技術が公開されてしまうため、競争上はあまり好ましいとはいえません。しかし反面、公開する事で利用者が増え、コミュニティが形成されて競合上有利になる点も指摘されます。MetaやDeepSeekがオープンソースを採用しているのも、後発ベンダーがコミュニティを形成して市場参入をしやすくする狙いもあるとされます。最近は中国発のモデルがオープンで公開されることが多いのですが、まさにこれが狙いという話と、加えて中国国内企業のAI利用を促進する、という国策も秘められているようです。
オープンウェイトモデルは、オープンソースほどでは無いにせよ、自社のノウハウや技術が公開されてしまうため、競争上はあまり好ましいとはいえません。しかし反面、公開する事で利用者が増え、コミュニティが形成されて競合上有利になる点も指摘されます。MetaやDeepSeekがオープンソースを採用しているのも、後発ベンダーがコミュニティを形成して市場参入をしやすくする狙いもあるとされます。最近は中国発のモデルがオープンで公開されることが多いのですが、まさにこれが狙いという話と、加えて中国国内企業のAI利用を促進する、という国策も秘められているようです。
OpenAIはもともと非営利団体として設立され、かつてはオープンウェイトでモデルを公開していたのですが、ビジネス寄りに舵を切ったために、ここ数年は公開をやめていました。今回の公開は6年ぶりだそうです。
今回の公開にあたっては、競合状況の激化により競合他社に対抗する必要が出てきたこと、OpenAIがこれまでのビジネス路線から元々の非営利路線へ戻ろうとしていることなどが背景にあるとされます。ユーザーにとってもメリットが大きいため、業界のトップベンダーがオープンウェイトでモデルを公開したことは好意的に捉えられていますが、それに加えて、ベンダー側の演算リソースの枯渇という現実的な問題もありそうです。
モデルがクローズにされていると、ベンダーは自社でサーバーやリソースを準備してサービスを提供しなければなりません。そのサービスを細分化して、無料で提供したり、APIで課金したりするわけです。しかしオープンソースやオープンウェイトなら、利用者がリソースを用意してその上でモデルを実行させることになります。これによって、利用者側にはプライバシーやデータが漏洩することが防げるなどのメリットがありますが、ベンダーにしてみれば自社の高価なリソースを使う必要がないことになります。
ご存じの通り、AI(特に生成AI)のサービスを稼働させるためにはこれまでとはケタ外れのリソース(CPUやGPUなど)が必要です。しかい今や世界中のデータセンターは満杯になり、それでも足りないため今後数兆円規模の投資が計画されている一方で、電力供給がネックになり、新規建設もままならないという状況も生まれています。AIの処理を、広く分散させなければならないという事情があるのです。
以前も書いたように、一般的なユーザーすべてが最先端のモデルをありがたがるわけでもなく、その必要もないわけで、ベンダー側の負荷を減らしながらAIを広く普及させていくための考え方として、オープンウェイトモデルは有効なのだろうと考えられます。今後、最高レベルのAIモデルは課金モデルで提供され、一般ユーザーが日常使うような、現在無料で提供されているモデルは、ユーザーのデバイスで実行されるようになるかもしれません。
【募集開始】ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日〜)
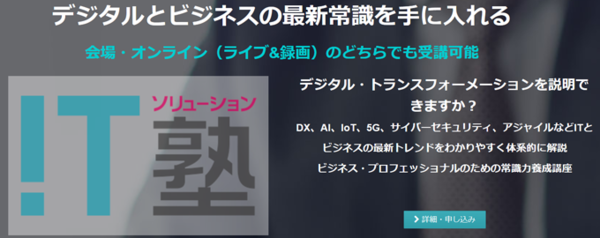 次期ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日 開講)の募集を開始しました。
次期ITソリューション塾・第50期(2025年10月8日 開講)の募集を開始しました。
ITベンダーにお勤めの方、ユーザー企業でDXやAIに取り組んでいる方向けに、毎週一回、さまざまなトピックを取り上げ、最新のITトレンドについて知識を深めていただきます。また、現在注目されているさまざまな技術が相互にどのように連携しているのか、歴史的な視点を交えて解説することで、技術の本質を理解していただきます。知識を真に内面化するためには、表層的な概念では無く、本質を理解することが重要です。
たとえば、AIサービスを賢く使いこなすためには、AIの仕組みやこれまでの進化の過程を理解することが重要です。そしてそれをビジネスに適用していくためには、AIそのものももちろん重要ですが、Web3やIoT、アジャイル開発/DevOpsといった分野にAIがどのような影響を与えていくのかを、幅広い視点から捉える必要があります。ビジネス環境全体を俯瞰し、各々のテクノロジーがどのように関連し、連携しているかを捉えることで、トレンドを掴むことができるのです。
ITソリューション塾では、最新技術の中身を紹介するだけで無く、他の技術との関わりや歴史的経緯を理解していただくことで、より広い視野の元で最新のトレンドを考えていただけるような講義を目指しています。
- 日程 :初回2025年10月8日(水)~最終回12月17日(水) 毎回18:30~20:30
- 回数 :全10回+特別補講
- 定員 :120名
- 会場 :オンライン(Zoomによるライブ配信と録画)
- 料金 :¥90,000- (税込み¥99,000) 全期間の参加費と資料・教材を含む
詳細なスケジュールは、こちらです。