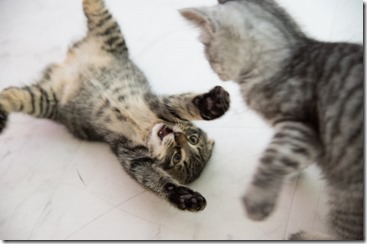その技術は先を見越していたのか?
@ITが、サイトオープン15周年だそうだ。長くIT業界にいる関係で、この機会にいくつかの記事を寄稿させていただいた。先日公開された「カリスマITトレーナーが見てきたActive Directory 15年の変遷」では、マイクロソフトのディレクトリサービスであるActive Directoryの進化の過程をまとめてみた。なお、タイトルは編集部によるものである。雑誌は常に大げさな表現が好きである。「カリスマITトレーナー」は「月刊Windows 2000 World」が最初に使ったものだ。
業界経験が長いと、ある技術が、思いもよらない使い方で脚光を浴びるシーンに出会うことがある。たとえば、「クラウドコンピューティング」の課金体系は、CPU、メモリ、ディスクなどの使用量に課金してコスト分配をしていたメインフレームモデルとそっくりである。「ダム端末とインテリジェント端末 ~歴史は繰り返さないが韻を踏む~」でも書いたとおり、Webアプリケーションは、メインフレームの端末動作とほぼ同じである。
メインフレーム全盛期に、クラウドのような仕組みやWebアプリケーションは想像していなかっただろうが、環境が変わって役に立つようになった例である。
最初から先を見越して登場したアイデアもある。
Active Directoryと、クラウドアプリケーションサービス(Office 365など)の連携に欠かせないシステムにAD FS(Active Directory Federation Services)がある。もともとは、異なるサービス間でユーザー名とパスワードを一元管理する汎用サービスとして登場したが、そもそもクラウドのことを考慮していたのだろうか。
AD FSの最初のバージョンは、Windows Server 2003 R2の頃に登場した。Windows Server 2003 R2の発表が2005年、「クラウド」という言葉が登場したのが2006年の「サーチエンジン戦略会議」とされているから、クラウドとは無関係のように思える。しかし、当時のマイクロソフトのドキュメントを見ると「第三者によって提供されたサービスとの連携」と書いてある。これは、まさにクラウドのことであり、クラウド(のようなサービス)を意識していたことが分かる。
Windows Server 2003では、「ブランチオフィス」という概念が注目された。ブランチオフィスは、遠隔地にある小規模なオフィスで、専任の管理者が不在で、通信回線が低速、物理的なセキュリティが十分ではないという問題がある。これを解決するために、ネットワーク帯域を効率よく使うファイル複製や、遠隔地ではなく最寄りのサーバーを優先的に選択する機能などが実装された。これらの技術は、現在、ブランチオフィスだけでなく、クラウド上のサーバーを効率よく使うためにも使われている。
クラウド上のサーバーは、物理セキュリティは十分であり、クラウド全体の管理者もいるから、ブランチオフィスの特徴は満たさない。しかし、インターネットを経由するために一般には低速(高遅延)で、自社のための管理者はいない(いるのはクラウド全体の管理者だけ)。この点ではブランチオフィスの特徴と似ているため、ブランチオフィスのための多くの技術がクラウド上で使われている。
たとえばActive Directoryの拠点を定義するサイト、通信量を節約する読み取り専用ドメインコントローラー(RODC)、効率の良いファイル複製機能DFS-R、ファイルサーバーの自動キャッシュ(BranchCache)などが代表的なものである。
また、Windows 2000から標準機能となった「リモートデスクトップサービス」の管理者モードは、遠隔地のサーバーを追加のライセンスなしに手軽に管理できる機能である。現在のWindows Serverはコマンドだけでも管理作業が可能だが、Windows Server 2003以前はそうもいかなかった。そもそもコマンドを覚えるのは面倒である。そのため、クラウド上にあるサーバーを管理するためには、リモートデスクトップは欠かせない。
では、2000年当時にリモートデスクトップサービスはクラウドを意識していたのだろうか。単に遠隔地のデータセンターしか考慮していないはずだが、これはクラウドでも同じことであり、結果的にはクラウドでも使われるようになった。
サーバーだけではない。Office 2007から採用された「リボン」はどうだろう。以前書いた記事「マウスボタンの数はいくつ?」ではこう書いた。
Microsoft Office 2007で導入された「リボン」も賛否、というか圧倒的に批判が多かった。当時のマイクロソフトの説明では、「グループ化しないとツールバーの領域が増えすぎる」というものだったが、ここに来て新しい意味が出てきた。ツールバーに配置されたツールボタンを指で操作するのはかなり難しいが、リボンに採用されたアイコンサイズならなんとか操作できるということだ。
Office 2007とiPhoneは同じ年に発表されているが、これは偶然なのだろうか。iPhone発表当時、iPadを予測した人は少ないと思うが、マイクロソフトは予測していたのだろうか。マイクロソフト謹製タブレットSurface RTにはOffice 2013が含まれるが、これがもしOffice 2003だったらとうてい使い物にならなかったに違いない。
前掲記事では明記しなかったが、リボンがタッチインターフェースを考慮していたかどうかはかなり疑わしい。2007年当時、Windows Vistaにはタブレット版が存在したが、当時のタブレットPCは専用のスタイラスペンを想定しており、指でタッチすることは考えていなかったはずである。タブレットPCのハードウェアガイドラインでも、スタイラスペンについての詳細な規定は存在したが、指で直接押す操作は定義されていない。誰にとっても使いやすいインターフェースを採用したら、たまたまタブレットでも使いやすかったということだろう。
このように、よく練られたアイデアは形を変えて生き残る。しかし、本当に生き残るかどうかはその時点では分からないのが困ったところだ。
コンピュータ技術の黎明期、半導体メモリが実用化される前に「水銀遅延線」というメモリがあった(さすがに私も生まれていない)。これを振り返ったあるエンジニアは
この技術は、まったく無駄でしたね。
現在につながる何の成果もなかった。
と断言していた。
そういうわけで、今回の結論は「よく考えられた技術は生き残り、先見の明があったと称賛されるが、それはあとにならないと分からない」という、何の教訓にもならない話である。とりあえず、今できる仕事をがんばりましょう。
▲コンピュータ技術と違い、子猫の価値は普遍性がある