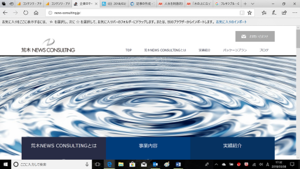トンガリ靴は出世しない。
行きつけのバーを見つけ、毎晩のように顔を出す。寿司屋のカウンターにひとり座り、のんびり酒を飲む。こんなとき、自分はオトナになったのだなあと、実感する。些細なことだが、こういう積み重ねが、人生を豊かにしてくれる。
ビジネスもまた、同じようなことが言えるだろう。憧れの先輩にちょっと褒められたり、社長から直々に仕事を頼まれたり。こんなとき、多少なりとも一人前として認められたのかなあと、小躍りしたくなるものだ。
人生にもビジネスにも、目標のようなものが必要だ。そこに到達して満足しているようでは、先がしれているが、それにしても、必ずや通過しておきたい〝仮の夢〟のような存在が、誰にでもあると思う。私にとっては、それが雑誌の連載だった。今月より、モノ系のファッション誌として人気を集める「Begin」(世界文化社)にて、1ページの連載を持つことになった。
雑誌はカルチャーをつくる
「POPEYE」「Hot-Dog PRESS」「MEN'S NON-NO」「Begin」・・・。40~50代の男性なら、若かりし頃に一度はハマった雑誌に違いない。ファッション・恋愛・音楽・グルメなど、若者はこれらの雑誌から情報を仕入れ、それをもとにオシャレをし、オンナを口説き、遊んだ。ちょっと上の世代が醸す時代感やオトナ感が妙に煌びやかに映り、これらの雑誌は若者のバイブルのような存在だった。
インターネットも携帯電話もない時代である。最先端の情報とは、毎月カネを出して買うもの。さすれば、自分は周囲から一歩抜きん出るに違いない、オンナからモテるだろうと思っていた。ほぼ全員、ガツガツした肉食系男子だったわけだ。
カネを出して買うのだから、損はしたくないと、雑誌の隅から隅まで読みまくる。そんなとき、ファッション誌のなかにおよそ不似合いなコラムに出会い、立ち止まる。オッサンが偉そうなことを言っていたり、流行りの文化人がワケの分からない業界話をしていたり、小僧にはまったく意味不明。でも、そんな異質な世界観が、かなり衝撃的だった。
確か「Hot-Dog PRESS」と記憶しているが、かの北方謙三氏が、若者の悩み相談に応じるという連載があったのだが、そこで彼がはいたむちゃくちゃなコトバを、今も鮮明に覚えている。ワキガに悩む青年に対して、「ワキガを嫌がるオンナだあ? そんな奴がいたらオレはなあ、そいつの顔をつかまえて、自分のワキの下に無理やり押し付けてやるんだよ」。悩みに答えているのか、いないのか。
ファッション誌ではないが、ちょっとエロいアイドル雑誌「Dunk」(1984~90年)も人気があった。私はこれを創刊号から買っており、お宝としていまだに大切に持っている。「Dunk」はアイドル雑誌なのに、本屋のオヤジがエロ本と勘違いし、いつもエロ本コーナーに置いていたため、買うのに勇気がいった。

先日、懐かしくなって「Dunk」の創刊号をめくってみたら、何とあのヤッサン(横山やすし氏)が、健全な青少年にムチャなことを語りかけるインタビューが載っていた。オトナの理論、しかもヤッサン流の独自な理論など、子どもが理解できるはずもない。でも今読むと、よく分かる。もし当時に理解できていたなら、それは大きな財産となったに違いない。
このように雑誌というのは、若者のカルチャーを育む機能を持っていた。ファッションのみならず、人生に必要なこと、もしかしたらビジネスに必要なことを、毎月語りかけてくれた。いつしか、ファッション面よりも、そんな硬質異質な連載の方に意識が向き始めるくらい、大きな影響力を持っていた。
今は就寝前、「Dunk」を創刊号から順に読んでいっているのだが、実に楽しい。当時流行っていたカルチャーや広告など、勉強になることも多い。
「Begin」で連載を持つというコト
さて、私は「Begin」で連載を持つことになった。実はこれ、個人的には、本を出版するのとはまた質を異にする喜びがある。それは本と雑誌の連載とでは、その価値や意味合いがまったく異なるから。
本は、「自分の名前」で出す、「一回きり」の作品。自分の書きたいコトを1冊にまとめ、それが書店に平積みされる光景を見ると、確かに達成感はある。しかし、無数の本が日々出版される現状においては、書店に自分の本が平積みされるのは、せいぜい1~2か月。並ばない書店もある。
これに対して雑誌の連載は、その雑誌の「ブランド」の名のもと、「毎月」出る作品。言い換えれば、「Begin」という人気ブランドの軒先を借りて、年間を通して、好きなコトが書ける。必然的にリーチする読者層は広がり、書店のみならずコンビニにも常に置かれるため、本とは明らかに影響力が異なる。
私は今春、初めてビジネス書を出版した。実はそのときから、いやもっと前、出版オファーのあった去年の春から、「いずれは雑誌の連載を3つ持とう」と考えていた。それは上述したように、本と雑誌の連載とでは、価値と意味合いが異なるということを、強烈に意識していたためだ。
「うちの連載はそれなりに注目を集めるから、それだけ責任も重いよ」。「Begin」の編集長と、何度目かのミーティングを行っているときのこと。彼は、私の肝を冷やすようなことを言った。雑誌の連載は、決して本記事のオマケではなく、雑誌の個性を表現する〝貴重なアクセント〟だと言う。私は自然と、「Hot-Dog PRESS」の北方氏の連載を想い出した。
「うちでかつて連載をお願いしていたのは、テリー伊藤さん、高城剛さん、辛酸なめ子さんなど、ものすごいメンツだからね」。その事実を知り、空恐ろしくなった。
連載タイトルは『仕事着八苦YOU!』
今年でちょうど25周年を迎えた「Begin」は、紛れもなく老舗ブランド。その存在感や影響力は衰えることなく、その証拠に、「Begin」で紹介される商品は、問い合わせが殺到し、瞬く間に完売することが度々あるという。廃刊が日常茶飯事の雑誌業界において、いまだに〝売れるムーブメント〟を作れる、強力媒体のひとつである。
そんな雑誌の編集長が、何をもって私に連載オファーをかけてきたのか? それはもう少し〝ビジネス色を強めたい〟という理由だった。私同様、当時の10~20代だった読者も、今や30代半ばにさしかかり、みな立派なビジネスマンに成長している。しかも、これからの組織を支える、重要なポジションに就きはじめる世代。ならばファッションだけでなく、彼らに向けて一味違うビジネスコラムを打ち出したいというのが、編集長の狙いだった。
かと言って、経済誌に掲載されるような本格的なビジネスコラムでは、「Begin」との相性が悪過ぎる。そこで、「ファッションアイテムを通して、ビジネスを語る」というテーマにしょうという話になった。これなら「Begin」らしい。
例えば、靴というアイテムをお題にする。そこで35歳近辺という読者層や、組織におけるポジションを意識し、「こういう靴を選んではイケナイ。なぜなら、こういう理由だから」といった具合で話を展開する。
靴というアイテムを「実際のビジネスでどう使うべきか?」「どのようなファッションをすれば、経営者や上司から認められるのか?」。もっと言えば、「デキるビジネスマンに見られるポイントは何処にあるのか?」。着地点は、あくまでもビジネス。ファッションに関するウンチクを語らないのが、従来のファッション誌の連載とは異なるところ。
なぜなら、私の本業はビジネスコンサルタント。付き合いのほとんどが企業経営者である。その一方で、現場社員のリアルな声もよく耳にする。その過程で、「もう少しこうすれば仕事がうまく回せるのに」と思うことが多々ある。そこで、コンサルタントという視点から、ファッションを絡めたビジネスの話をしようということになった。
『仕事着八苦YOU!』。これが連載タイトル。八苦YOUは、ファッキュー! にひっかけたコトバ。ここからも想像できるように、基本的に、ダメなファッションやイケてない仕事ぶりを、ダメ出ししていくという内容。やや辛らつなコラムだ。
と、このように何度も打ち合わせを重ねて連載テーマを決め、原稿を何度か書き直し、連載1回目の「トンガリ靴は出世しない」ができた。それが16日発売の「Begin1月号」。キリが良いので、1月号からスタートすることになった。
今、40代の雑誌編集長たちが熱いのですよ
「まだ個性が出てないなあ。荒木さんの〝見ている景色〟が見たいんだ。コクを出すって言うか、やっぱりコンサルタントって違うみたいな」。
連載2回目のミーティングの冒頭、さっそく編集長から注文が入る。1回目の原稿にO.K.を出したものの、彼のイメージとは少し違ったようだ。ダメ出しをされながら、感心した。それは、編集長の言語感覚というか表現法。
〝見ている景色〟が見たい。まるで映画のディレクターのような台詞。漠としているが、言わんとしていることはよく理解できた。文章を文字でなく立体的に捉え、映像のようにイメージで切り取る。人気雑誌の編集長はやはりタダものではない・・・。
書籍の編集者なら、「ここの文章をもう少し分かりやすくしてください」といった表現を使う。要は、具体的な論理性や正確性を求める。Webの編集者なら、「タイトルはキャッチーで」など、ネット上でフックになりやすいインパクトや即効性を重視する。編集という同じ仕事なのに、ターゲットにする読者、媒体、ジャンルによって、求められる文章はかなり異なるのだ。
「Begin」の編集長とのやりとりは、すっかりビジネス書の執筆に慣れていたアタマには、とても新鮮かつ刺激となった。書く媒体が変わると、自分の文章力を磨けると同時に、思ってもいなかった〝新しい視野〟が手に入るからだ。
ミーティングの最中、連載に入れるイラストの話になった。そのとき、私はたまたま、執筆中の2冊目に挿入するラフスケッチを持っていた。担当編集者から、なぜかイラストを書いてくれと頼まれていたので、それを見せてみた。
「おお、ヘタウマで良い! イラストも書く?」なんて。
こんな調子で、雑誌の連載はスタートすることになった。しかし、私も、編集長も、担当編集者もいたって真面目。仕事のレベルに厳しく、妥協を許さず、思考にかける時間を惜しまず、とことんやり抜く。だからこそ、雑誌という商品は、日本のカルチャーを作ってこれたのだろうと想う。
現在、複数の雑誌から、連載を書かないかという話がきている。そんな編集長は、たいてい40代。彼らと話をしていて感じるのは、雑誌という紙媒体に対する強烈なこだわりと、自分の雑誌ブランドへの熱い想いと、ひいては、読者に対する旺盛なサービス精神。
雑誌はカネを払って買ってもらう読み物なんだ。うちはよその雑誌とは違うんだ。こだわりと野望を持って誌面を作っていこうじゃないか・・・。40代の編集長たちからは、殺気にも似た、尋常でないパワーが伝わる。みな、良い目つきをしている。
そんな編集長たちに会うたびに、ふと想うのだ。私が10代だった頃、雑誌の連載を読んで衝撃を受けたとき、その背後には、こうした野望を抱えた作り手たちがいたのだと、想像するのだ。熱い想いが伝わったからこそ、いつまでも忘れない記憶となり、好きなファッションやカルチャーが生まれ、それが気づかぬうちに、自分の一部を形成しているのだろう。
雑誌とは、消耗品ではないのだ。
連載の話をもらってから、十数年ぶりに「Begin」を買ったが、やけに新鮮に見えた。靴にしろカバンにしろ、およそ今の自分は買わないだろう・選べないだろうモノが、誌面に並んでいたから。お気に入りのブランドで決め打ちしてしまっているため、いつの間にか視野が狭まっていることに気づかされた。
誌面のモノたちを眺めているうちに、当時のワクワクした感覚が蘇ってきた。・・・そんな感じで、連載スタート。
(荒木NEWS CONSULTING 荒木亨二)
ファッションや音楽などライフスタイルに関するコラムも多数――。マーケティングを立て直す専門のコンサルティングです。詳しくは下記Webサイトをご覧ください。